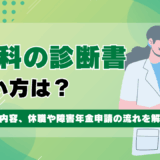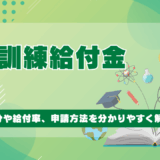失業保険と傷病手当金は目的と管轄が異なり、同時受給はできません。失業保険は働ける状態が前提で、傷病手当金は働けない状態が前提のため、状況に応じた使い分けが重要です。
この記事では、失業保険と傷病手当金の違い、同時受給が不可な理由、退職タイミング別の最適ルート、ケース別の申請優先順位、受給期間延長の申請方法まで解説します。
失業保険と傷病手当金の違いは?
失業保険と傷病手当金の二つの制度は名称が似ていますが、目的と管轄が明確に異なります。
| 項目 | 失業保険 (雇用保険の基本手当) | 傷病手当金 (健康保険) |
|---|---|---|
| 目的 | 失業中の生活を支え、早期再就職を促進する給付 | 業務外の病気・けがで働けない間の収入補填 |
| 要件 | ①ハローワークで求職申込み済み ②就職の意思・能力があり失業状態 ③被保険者期間: 自己都合は「過去2年で通算12か月以上」 特定理由・特定受給は「過去1年で通算6か月以上」 ※病気・けがですぐ就職できない状態は対象外。 | ①業務外の療養で労務不能 ②連続3日の待期後、4日目から支給 ③給与支給がない(又は少ない)こと |
| 支給額 | 「基本手当日額」=離職前賃金(賃金日額)のおよそ50〜80% (60〜64歳は45〜80%) ※年齢ごとの上限あり | 「標準報酬日額×2/3」が1日あたりの支給額 |
| 期間 | 所定給付日数:おおむね90〜360日 受給期間:離職翌日から原則1年 (病気・出産等で最長3年まで延長可) | 支給開始日から通算1年6か月 (同一傷病での上限) |
| 窓口 | ハローワーク(公共職業安定所) | 加入している健康保険 (協会けんぽ/健康保険組合) |
参考:
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
失業保険と傷病手当金の同時受給は不可
傷病手当金は「働けない状態(労務不能)」が前提であり、失業保険は「働ける状態にあるが、仕事がない」が前提です。このため、両方の条件を同時に満たすことはないため、同時受給は原則としてできません。
公的制度では、どちらか一方の期間を優先し、もう一方の期間は「延長」や「切替」で対応する必要があります。
迷ったら「当面の収入確保」と「回復見込み」で選ぶのがおすすめです。
- 当面の収入確保
退職直後で療養が必要な場合、まずは審査に通りやすい健康保険の傷病手当金を申請し、収入を確保しながら療養に専念するのが賢明です。
- 回復見込み
病状が長期化しそうな場合は、失業保険の権利を温存するために「受給期間の延長」手続きを最優先します。
失業保険と傷病手当金の退職タイミング別の最適ルート
失業保険と傷病手当金のどちらを優先すべきかは、「いつ病気になったか」「健康保険の被保険者資格があるか」によって最適なルートが変わってきます。経済的な損をしないための最適なルートを解説します。
在職中に病気発症→退職する場合は傷病手当金を継続給付
退職前にすでに病気が発症し、療養が必要な状態であれば、退職後も健康保険の傷病手当金の継続給付を受け取るのが最適です。なぜなら、退職直後から収入を確保でき、療養に専念できるためです。失業保険は、療養後に「受給期間の延長」手続きを行えば権利を最長4年間温存できます。
なお、継続給付の条件(退職日までに1年以上の被保険者期間がある、退職日に出勤しない)を必ず満たすようにする必要があります。
退職後に病気が判明した場合は失業保険の受給期間の延長手続き
退職後にハローワークで求職申込みをする前に病気が判明し、長期療養(30日以上)が必要になった場合は、まず失業保険の「受給期間の延長」手続きを行うのがベストです。
このケースでは、健康保険の傷病手当金の継続給付は対象外となるため、受給期間の延長手続きをしておくことで、本来1年間の受給期間を最長4年間まで伸ばすことができ、回復後に失業保険を全額受け取る権利を確保できます。
休職中に退職へ切替える場合は傷病手当金の継続給付
すでに休職して傷病手当金を受給中に退職が決まった場合も、引き続き傷病手当金の受給を継続できます(最長通算1年6ヶ月の範囲内)。
退職後もそのまま傷病手当金を受け取り、回復を待ってから失業保険に切り替えます。この際も、離職日の翌日から30日経過後、速やかにハローワークで失業保険の「受給期間の延長」手続きを行うことを忘れないでください。
ケース別!失業保険と傷病手当金のどっちを先に申請すべき?
体調が不安定な中で、どの手続きを優先すべきか迷う方は少なくありません。ここでは、「働ける状態」か「働けない状態」かの医師の診断に基づき、生活保障を確保するための申請の優先順位を明確にします。
すぐ働けない(労務不能)|傷病手当金 → 回復後に失業保険
医師の診断により「労務不能」である場合は、健康保険の傷病手当金を最優先で申請します。これは、生活保障の観点から最も重要であるためです。
この間、ハローワークで失業保険の「受給期間の延長」手続きを行い、失業保険の受給開始を後回しにします。体調が回復し、医師から「就労可能」の証明が出てから、ハローワークで失業保険に切り替えます。
すぐ働ける|失業保険 → 求職活動
病気やケガがすでに完治しており、すぐに求職活動を開始できる状態であれば、通常通りハローワークで失業保険を申請し、求職活動を行いましょう。
働けるか微妙|まず医師判定→延長申請で受給権を温存
体調に不安があり、すぐに就職できるかどうかの判断が難しい場合は、まず医師の診断(労務不能かどうか)を仰ぎます。労務不能と判断されたら「傷病手当金」へ。
どちらに転んでも損をしないように、失業保険の「受給期間の延長」手続きを最優先で行い、受給権を温存しておくのが最善策です。
失業保険を後回しにする方法
失業保険を後回しにするための具体的な手続きが「受給期間延長の申請」です。
失業保険の受給期間は原則離職日の翌日から1年間ですが、病気やケガで働けない期間はこの受給期間に含まれてしまいます。この手続きを行うことで、受給期間を最長で4年間まで延長できます。
| 申請期限 | 延長事由(病気・ケガ)が生じた日の翌日から30日を経過した日以降、早めに申請します。 |
| 必要書類 | 受給期間延長申請書、離職票、医師の診断書(病気やケガで働けないことを証明するもの) |
この手続きを完了させておけば、療養期間が長引いても、回復後に安心して失業保険を受け取ることができます。
失業保険と傷病手当金に関するよくある質問
失業保険と傷病手当金に関するよくある質問を紹介します。
- 傷病手当金を受けながら求職登録だけしてもいい?
- いいえ、できません。
傷病手当金は「働けない状態」が前提であるため、ハローワークで「働ける意思がある」ことを示す求職登録は、傷病手当金の受給条件に反します。療養に専念しましょう。
- パート・派遣・フリーランスでも支給対象になる?
- パート・派遣社員は、健康保険や雇用保険に加入していれば、雇用形態に関わらずこれらの制度の対象となります。フリーランス(個人事業主)は、雇用保険や健康保険(社会保険)に加入していないため、原則として失業保険や傷病手当金の対象外となります。
- 休職→退職に切替えたら手続きはやり直し?
- いいえ、手続きの大部分は継続されます。健康保険の傷病手当金はそのまま継続受給され、失業保険についても「受給期間の延長」手続きが適用された状態となります。
ただし、退職後は被保険者資格が変わるため、ハローワークでの届け出(離職票の提出)は必要です。
まとめ
失業保険と傷病手当金は目的と管轄が異なり、同時受給は不可です。傷病手当金は働けない状態が前提で、失業保険は働ける状態が前提のため、両方の条件を同時に満たすことはありません。
退職タイミング別の最適ルートは3つです。在職中に病気発症して退職する場合は傷病手当金を継続給付し、失業保険は受給期間の延長手続きで権利を温存します。退職後に病気が判明した場合は失業保険の受給期間の延長手続きを行い、本来1年間の受給期間を最長4年間まで伸ばします。休職中に退職へ切替える場合は傷病手当金の継続給付を受け、回復後に失業保険に切り替えます。
ケース別の申請優先順位は、すぐ働けない場合は傷病手当金を申請し回復後に失業保険、すぐ働ける場合は失業保険を申請して求職活動、働けるか微妙な場合はまず医師判定を仰ぎ受給期間の延長手続きで受給権を温存するのがおすすめです。
失業保険を後回しにする方法は受給期間延長の申請で、延長事由が生じた日の翌日から30日を経過した日以降に申請します。失業保険と傷病手当金の使い分けで損をしたくない方はぜひ参考にしてみてください。