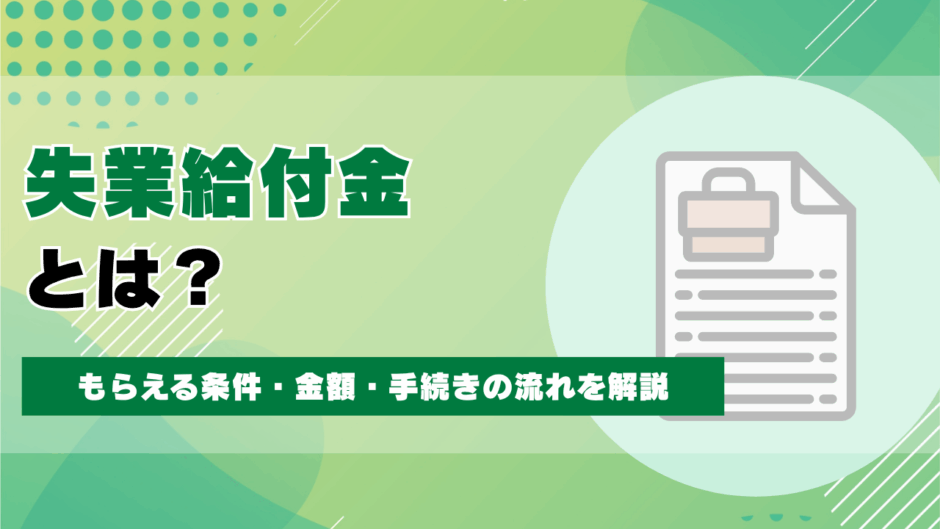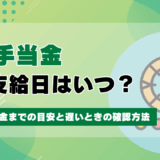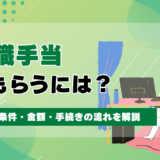仕事を辞めたあと、「失業給付金ってどんな制度?」「自分ももらえるの?」と気になる方は多いでしょう。失業給付金(正式名称:雇用保険の基本手当)は、一般に「失業保険」とも呼ばれ、再就職までの生活を支える国の制度です。
条件や手続きを正しく理解しておくことで、もらい損ねや手続きミスを防ぎ、安心して次の仕事探しに専念できます。
この記事では、失業給付金の仕組み・受給条件・支給金額の目安から、注意点やよくある質問までをわかりやすく解説します。初めて申請する方でも、全体の流れを理解することでスムーズに手続きを進められるでしょう。
まず知っておきたい失業給付金の基本
失業給付金の全体像を先に押さえると、このあとの条件や手続きが理解しやすくなります。
ここでは、制度の目的と仕組み、退職金や再就職手当との違い、そして誰が対象になるのかを順に見ていきます。
失業給付金の目的と仕組み
失業給付金は、雇用保険に基づいて支給される「生活支援+再就職支援」の制度です。
働く意思と能力があるにもかかわらず職を失った人に対し、再就職までの生活を一時的に支える役割を果たしています。
- 目的:生活の安定と早期再就職の支援
- 財源:税金ではなく、雇用保険料から支給
- 支給元:厚生労働省(運営)/ハローワーク(申請・給付)
参考:厚生労働省「基本手当について」
退職金や再就職手当との違い
失業給付金と似た名称の制度は複数ありますが、それぞれの目的や支給時期、対象者が異なります。
<主な制度の違い>
▼失業給付金
- 目的:失業中の生活支援と再就職の促進
- 支給時期:退職後、待機期間・給付制限期間終了後
- 対象者:雇用保険の加入者で、失業状態にある人
- 申請先:ハローワーク
▼退職金
- 目的:勤務への慰労・功労報奨
- 支給時期:退職時(会社の規定による)
- 対象者:会社の退職金制度の対象者
- 申請先:勤務していた会社
▼再就職手当
- 目的:早期の再就職を促すための給付金
- 支給時期:再就職が決まった後
- 対象者:失業給付金の受給資格者で、一定の要件を満たした人
- 申請先:ハローワーク
▼高年齢求職者給付金
- 目的:65歳以上で離職した人の生活支援
- 支給時期:一時金として一括支給
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者で、失業状態にある人
- 申請先:ハローワーク
失業給付金=雇用保険の「基本手当」です。
退職金のような企業からの支給金や、再就職手当のような「就職後の報奨」とは異なります。
参考:厚生労働省「再就職手当のご案内(PDF)」
参考:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>(PDF)」
受給対象になる人の特徴
雇用保険に加入していれば、正社員・契約社員・派遣社員・パートなど雇用形態に関係なく対象になります。
ただし、勤務時間や日数が一定基準を満たしていることが必要です。
- 週20時間以上働いている
- 31日以上の雇用見込みがある
- 雇用保険に加入している
これらを満たすことで、基本手当の申請資格を得られます。
失業給付金をもらうための条件と必要書類
申請は「誰でもOK」ではありません。受給の可否は、加入期間・離職理由・求職活動の有無という基本条件と、揃えるべき書類で決まります。
ここでは、判定に使われる基準と提出物、注意点を具体的に確認します。
受給できる3つの基本条件
失業給付を受けるには、雇用保険の加入実績や離職理由、再就職への意思など、一定の要件を満たす必要があります。
以下の3点を満たしているかを確認しておきましょう。
雇用保険の加入期間
一般的には「退職前の2年間に通算12か月以上」が条件ですが、会社都合や特定受給資格者の場合は「離職前1年間に6か月以上」で受給できる場合もあります。失業給付は「失業中の生活支援」を目的とした制度のため、一定期間の保険加入が前提になります。短期雇用や週20時間未満のパート勤務など、被保険者に該当しない期間は対象外です。
離職理由
自己都合・会社都合・特定理由離職者のいずれかに該当することが求められます。離職理由によって給付開始までの期間が異なり、「会社都合退職」は早く受給できる一方で、自己都合退職は、待機期間(7日)に加えて原則1か月の給付制限があります。
ただし、過去5年以内に3回目以降の離職がある場合などは、3か月の給付制限となることがあります。離職票に記載された内容に誤りがないか、必ず確認しておきましょう。
求職活動の意思と能力
就労可能であり、再就職に向けて活動していることが必要です。失業給付は「働く意思のある人」が対象であり、体調不良やケガで働けない場合は、傷病手当金など別の制度が適用されます。ハローワークでの求職登録と定期的な失業認定が受給の前提です。
特定理由離職者・特定受給資格者とは
離職理由によっては、自己都合でも会社都合に近い扱いとなり、待機期間なしで受給できるケースもあります。
主な例を以下にまとめました。
- 会社の倒産、解雇、雇止め(契約更新されない)
- 上司や同僚からのハラスメント
- 家族の介護・看護
- 配偶者の転勤による離職
該当するかどうかは、離職票の記載内容で判断されるため、離職理由が実情と異なる場合は訂正申請が必要です。
参考:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
必要書類と注意点
申請に必要な書類は以下の通りです。
▼失業保険の申請に必要な主な書類
- 離職票1・2: 退職理由や賃金情報を証明する書類。離職理由が誤っていないか必ず確認。
- 本人確認書類: 運転免許証・マイナンバーカードなど。写真付きが望ましい。
- 印鑑・通帳: 振込口座を確認するために使用。銀行名義は本人のみ。
- 雇用保険被保険者証: 雇用保険の加入実績を証明。紛失した場合は再発行が可能。
離職票の記載内容に誤りがあると、不支給になることがあります。不明点は、ハローワークで早めに相談しましょう。
いつから・いつまで・いくらもらえる?支給の目安
「いつ始まり・いつまで続き・いくら受け取れるか」は計画を立てるうえで重要です。
ここでは、支給開始までの時系列、所定給付日数の考え方、金額の算出方法を見ていきましょう。
支給が始まるまでの流れ

退職後から初回の振込までの一般的な流れは以下の通りです。
- 退職
- ハローワークで離職票を提出
- 待機期間(7日間)
- 給付制限期間(自己都合は原則1か月)
- 受給資格決定・初回認定
- 振込開始(おおよそ退職から1〜2か月後)
自己都合退職か会社都合退職かによって、給付制限の有無や期間が変わります。
受給できる期間の目安
所定給付日数は、離職理由・年齢・勤続年数によって変わります。一般の被保険者では、会社都合退職が最長330日、自己都合退職は勤続10年以上・45歳以上で150日が上限です。なお、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」として一時金扱いになります。
また、失業給付の受給は離職日の翌日から原則1年以内に終了する決まりがあるため、この期間を過ぎると未支給分があっても受け取れません。再就職が決まった場合は、残りの給付日数に応じて再就職手当が支給されることもあります。
| 離職理由 | 勤続年数 | 給付日数(目安) |
|---|---|---|
| 自己都合退職 | 1年未満〜10年以上 | 90〜150日 |
| 会社都合退職 | 1年未満〜20年以上 | 90〜330日 |
| 特定理由離職 | 条件により異なる | 90〜150日程度 |
支給額の計算方法と上限・下限
支給額は以下の計算式で求められます。
基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)
賃金日額は「退職前6か月の総支給額 ÷ 180日」で算出します。
給付率は収入が低いほど高く設定され、最大で80%。上限・下限は毎年見直されるため、最新の金額は厚生労働省の発表を確認しましょう。賞与や退職金は含まれない点にも注意が必要です。
受給中に注意すべきこと
受給開始後は、申告や働き方、社会保険・扶養の扱いなどで思わぬ減額や不支給につながることがあります。
ここでは、アルバイト・内職の申告方法や、社会保険・扶養の扱いで注意しておきたいポイントを解説します。
副業やアルバイトは必ず申告が必要
受給期間中にアルバイトや副業をした場合は、必ずハローワークに申告が必要です。
働いた時間や日数、金額によって支給額が減ることがあります。
申告を怠ると「不正受給」と見なされ、全額返還や追加納付の対象になることもあるため注意が必要です。
就労・内職・手伝いの違いを整理
働き方によって、失業認定の扱いが変わります。
「短期バイト」「家業の手伝い」「在宅ワーク」なども、内容によっては就労と見なされる場合があります。
どんな仕事でも、行う前にハローワークへ相談しておくと安心です。
| 行動例 | 申告の要否 | 支給への影響 |
|---|---|---|
| 正社員・パートとしての勤務 | 必要 | 支給停止(就職扱い) |
| 単発バイト(1日) | 必要 | 日数分の減額 |
| 家業の手伝い・内職 | 必要 | 状況により減額または停止 |
社会保険や扶養の注意点
失業中は、健康保険や年金の加入先が変わる場合があります。
会社の保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するかを選ぶ必要があり、配偶者の扶養に入る場合は、失業給付の金額や受給期間によって条件が変わります。扶養の判断基準は保険組合によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、国民年金は「免除制度」や「猶予制度」を活用できるため、経済的に負担が大きいときは早めに自治体へ相談しましょう。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
まとめ
失業給付金は、生活を支えるだけでなく、次の仕事へ踏み出すための再スタートを支援する制度です。受給条件や手続きを正しく理解しておけば、想定外のトラブルや「もらい損ね」を防げます。
焦って再就職先を選ぶのではなく、自分のペースで方向性を見直すことも大切です。制度をうまく活用しながら、心身を整え、次のキャリアに向けて準備を進めていきましょう。