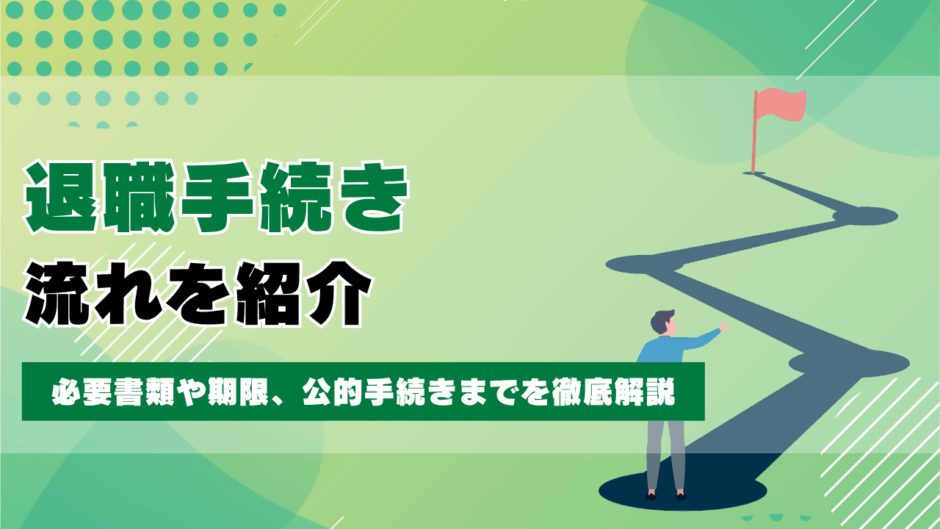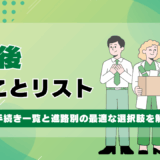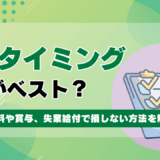退職手続きは、就業規則の確認から退職意思の伝達、退職届の提出、有給消化と引継ぎ、退職後の公的手続きまで計画的に進める必要があります。退職の意思は通常退職希望日の1〜2ヶ月前に直属の上司に伝達し、退職後は健康保険が20日以内、年金が14日以内と期限が短い手続きが続きます。
この記事では、退職手続きを始める前のチェックリスト、手続きロードマップ、必要な書類一覧、退職後の公的手続きまで解説します。
退職手続きを始める前に確認したいチェックリスト
退職手続きをトラブルなくスムーズに進めるためには、事前の情報収集が不可欠です。まずは以下の3つの項目を必ず確認しましょう。
チェック1|就業規則の確認
退職願の提出期限、有給休暇の取り扱い、そして退職後の義務について確認します。特に重要なのは、申告期限(通常、退職日の1〜2ヶ月前)です。
なお、法律上(民法第627条)では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば退職できると定められています。しかし、円満退職を目指す上では、就業規則の規定を尊重し、引継ぎ期間を十分に確保することが推奨されます。
また、競業他社への転職を禁止する競業避止義務や、在職中に知り得た情報を漏らさない秘密保持義務についても確認し、違反しないよう注意が必要です。
参考:労働基準監督署「退職の申出は2週間前までに」
チェック2|退職理由の整理
退職理由は、ハローワークで失業保険(基本手当)を受給する際の離職区分に直結します。
| 退職理由 | 離職区分 | 給付制限 |
|---|---|---|
| 自己都合 | 一般の離職者 | あり(待期期間7日間+給付制限1ヶ月) |
| 会社都合 | 特定受給資格者・特定理由離職者 | なし(待期期間7日間のみ) |
パワハラ、解雇、体調不良による療養などの場合は、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、給付制限がなく、支給開始が早まる可能性があります。自身の退職理由がどちらに該当するか、またパワハラなどによる会社都合の退職の場合は証拠の有無を整理しておきましょう。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
チェック3|次の収入計画
退職後の生活費を確保することは最優先事項です。次の職場が決まっているか、当面の生活費の貯蓄(最低3〜6ヶ月分)があるかを確認しておきましょう。
また、失業保険の受給資格(被保険者期間)と概算額を試算し、また病気療養が必要な場合は傷病手当金の継続給付の可否を確認しておきます。
いよいよ退職を決めたら?手続きロードマップ
退職意思の伝達から公的手続きまで、時系列に沿って計画的に進めましょう。
自社の就業規則(特に退職の申告期限)を確認します。申告期限は通常、退職希望日の1〜2ヶ月前と定められています。その上で、残っている有給休暇の日数や、業務の引継ぎに必要な期間を考慮し、具体的な退職希望日を仮決めします。この段階で、直属の上司に伝える退職理由と、誰に、いつ伝えるかを明確にしておきましょう。
退職の意思は、就業規則に定められた申告期限を守り、直属の上司に口頭で伝達します。その後、退職日や引継ぎ方法について合意を取り付けます。円満退職を目指す場合は、誠意をもって相談ベースで進めることが重要です。
会社の指示に従い、退職届または退職願を作成し、提出します。提出後は撤回が難しくなるため、慎重に判断しましょう。提出前に控えを必ず保管し、提出日を記録しておきます。
- 有給消化:会社側と調整し、残っている有給を計画的に消化します。
- 引継ぎ:後任者への引継ぎを円滑に進めるための計画表を作成し、マニュアルや資料を整備します。
- 返却物・アクセス権の整理:社用PC、社員証、健康保険証などの貸与物の返却準備と、社内システムへのアクセス権限の整理を行います。
最終出社日は、関係者への挨拶を済ませます。退職日には、会社から離職票、源泉徴収票などの必要書類を受け取ることを確認し、健康保険証などの貸与物を返却します。
退職後は期限が短い手続きが多いため、速やかに雇用保険(ハローワーク)、健康保険、国民年金、税金などの切り替えや申請手続きを進めます。
退職手続きで必要な書類一覧
退職時、会社と役所でやり取りする主な書類を紹介します。
会社から受け取るもの
- 離職票:失業保険(基本手当)の申請に最も重要です。
- 雇用保険被保険者証:次の会社に提出するか、失業保険申請時に使用します。
- 源泉徴収票:確定申告や次の職場の年末調整に必要です。
- 退職証明書:国民健康保険の加入や、転職先の入社手続きで必要な場合があります。
- 健康保険資格喪失証明書:国民健康保険加入や家族の扶養に入る際に必要です。
関連記事:「離職票はいつ・どこで提出する?ハローワークでの使い方と事前に確認すべきこと」
会社に提出する・返却するもの
- 退職届:退職を証明する正式な書類です。
- 健康保険証:速やかに会社経由で返却します。
- 貸与物:社用PC、携帯電話、社員証、名刺など。
- 機密保持誓約書:退職時に秘密保持に関する誓約書にサインを求められる場合があります。
退職後すぐにやるべき役所・保険・年金の手続き
退職後は、公的な保険や年金の手続きに期限が設けられています。
健康保険|任意継続/国民健康保険/家族の扶養の選び方
退職日の翌日から健康保険の資格を失うため、20日以内に以下のいずれかを選択し手続きが必要です。
- 任意継続:会社の保険に最長2年間継続加入。保険料は全額自己負担となります。
→手続き期限は退職日の翌日から20日以内 - 国民健康保険:お住まいの市区町村役場で加入します。
→手続き期限は退職日の翌日から14日以内 - 家族の扶養:配偶者など家族の健康保険の被扶養者になる(収入要件あり)。
参考:全国健康保険協会「会社を退職するとき」
年金|第2号→第1号(または第3号)への切替
会社員(厚生年金=第2号被保険者)は、退職日の翌日から14日以内に以下のいずれかに切り替える必要があります。
| 国民年金(第1号) | 市区町村役場で手続き。 |
| 配偶者の扶養に入る(第3号) | 配偶者が第2号被保険者の場合、配偶者の勤務先を通じて手続き。 |
参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
雇用保険|求職申込みと初回認定までの流れ
離職票が届き次第、速やかにハローワークで求職申込みを行います。その後、説明会参加や待期期間(7日間)を経て、失業の初回認定日に失業認定を受けることで、失業保険(基本手当)の給付が始まります。病気療養などで求職活動ができない場合は、「受給期間延長」の手続きが必要です。
関連記事:「失業保険の受給条件とは?もらえる人・もらえない人の違いをわかりやすく解説」
まとめ
退職手続きを始める前に確認したいチェックリストは、就業規則の確認、退職理由の整理、次の収入計画の3つです。就業規則では退職願の提出期限を確認し、退職理由は失業保険の離職区分に直結するため自己都合か会社都合かを整理します。
退職手続きロードマップは、退職意思の決定と初動、退職意思の伝達、退職届・退職願の提出、有給消化と引継ぎ、最終出社〜退職日、退職後の公的手続きの6ステップです。退職の意思は就業規則に定められた申告期限を守り、通常は退職希望日の1〜2ヶ月前に直属の上司に口頭で伝達します。
退職手続きで必要な書類は、会社から受け取るものとして離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書があり、会社に提出する・返却するものとして退職届、健康保険証、貸与物、機密保持誓約書があります。
退職後すぐにやるべき手続きは、健康保険は退職日の翌日から20日以内に任意継続・国民健康保険・家族の扶養のいずれかを選択、年金は退職日の翌日から14日以内に国民年金または配偶者の扶養に切り替え、雇用保険は離職票が届き次第速やかにハローワークで求職申込みを行います。
退職手続きで損をしたくない方はぜひ参考にしてみてください。