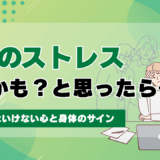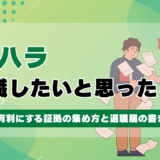心療内科の診断書は、休職・欠勤を申請するとき、保険申請や傷病手当金の手続きのときに必要です。医師が就業・通学が困難であり休養が必要と判断した際に発行され、費用は3,000円〜6,000円程度が相場です。病名を会社に知られたくない場合は、医師に相談することでぼかした表現で記載してもらうことも可能です。
この記事では、心療内科の診断書が必要なとき、記載内容、もらう流れ、費用と発行期間、提出時の注意点、できること・できないこと、よくある質問まで解説します。
心療内科の診断書はどんなときに必要?
診断書は、単なる「お休みのお願い」ではありません。休職の正当性を客観的に証明し、労働者の権利を守るための重要な役割を担っています。また、会社側にとっても、従業員の健康状態を正確に把握し、適切な労務管理を行うための指針となります。
具体的には、以下のような場面で必要となります。
- 仕事のストレスやうつ症状で「休職・欠勤」を申請するとき
- 学校や試験を「欠席・延期」したいとき
- 保険申請や公的手当(傷病手当金など)の手続きのとき
医師が医学的な見地から「就業・通学が困難であり、休養が必要」と判断した際に発行されます。
参考:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
診断書にはどんな内容が書かれるの?
診断書には、休職や手当の申請に必要な最低限の情報が記載されます。
| 記載項目 | 内容 |
|---|---|
| 患者情報 | 氏名、生年月日、住所など |
| 傷病名 | うつ病、適応障害など、医師が診断した病名 |
| 発病年月日 | 症状が出始めた日 |
| 症状・経過 | 具体的な心身の症状や、これまでの治療経過 |
| 今後の見通し | 治療継続の必要性や、復職の見込みなど |
| 休職の必要性 | 「上記の傷病のため、〇ヶ月間の休養を要する」といった記載 |
| 医療機関情報 | 病院名、所在地、医師名、押印など |
「うつ病」などの具体的な病名を会社に知られたくない場合は、医師に相談することで「ストレスによる体調不良」や「自律神経失調症」など、ぼかした表現で記載してもらうことも可能です。
心療内科で診断書をもらう流れ
まずは、かかりつけ医または専門の医療機関に予約を入れましょう。初診の場合は予約が埋まっていることも多いため、早めの連絡が大切です。
診察時に、症状(眠れない、食欲がない、意欲がわかない等)や困っていること(仕事に行けない等)を具体的に伝えます。
医師に「会社を休むために必要」など、診断書が必要な理由を説明し、発行を依頼します。
発行された診断書を受け取ります。氏名や期間など、内容に間違いがないかその場で確認しましょう。
会社の上司や人事部、学校など、必要な場所に提出します。
最近では、通院の負担を減らすために「オンライン診療」で診察から診断書発行(郵送)まで対応しているクリニックも増えています。
診断書の費用と発行にかかる期間
診断書の発行は、病気の治療そのものではないため健康保険の適用外(自費診療)となります。また、医療費控除の対象にもなりません。
| 診断書の種類 | 費用相場 |
|---|---|
| 一般的な診断書(休職・休学用) | 3,000円~6,000円程度 |
| 自立支援医療用診断書 | 5,000円~7,000円程度 |
| 精神障害者保健福祉手帳用診断書 | 5,000円~6,000円程度 |
| 障害年金用診断書 | 8,000円~15,000円程度 |
一般的な診断書であれば、医師の判断ですぐに書ける場合、即日発行されることが多いです。ただし、書類の種類や病院の混雑状況によっては数日かかる場合もあります。紛失時の再発行は可能ですが、再度費用がかかる場合があるため注意しましょう。
会社や学校に診断書を出すときの3つの注意点
- 原本を人事・総務または担任宛に提出
基本的には原本を提出します。手元にコピー(控え)を取っておくと、後で期間などを確認する際に便利です。 - 病名を知られたくない場合は「体調不良」などにしてもらう
前述の通り、病名の記載は医師と相談可能です。 - メール添付での提出を認めている会社もあり
体調が悪く出社が困難な場合は、郵送やPDFデータのメール添付で対応してくれる会社も増えています。まずは電話やメールで相談してみましょう。
企業には従業員の詳細なプライバシー(具体的な病名や治療内容の深部)までを聞き出す権利はないため、最低限の情報で休職手続きは進められます。
心療内科の診断書でできること・できないこと
診断書は万能ではありません。その効力範囲を理解しておきましょう。
| 項目 | できる | できない |
|---|---|---|
| 休職・欠勤の証明 | ○ | – |
| 傷病手当金の申請 | ○ | – |
| 就職・転職に有利に働く | × | – |
| 精神疾患の確定診断書として法的効力 | △(限定的) | – |
診断書はあくまで「現時点での治療と休養の必要性」を示すものであり、裁判などでの絶対的な法的証拠書類とは性質が異なります。
診断書をもらったあとは傷病手当金を受け取りながら休職をしよう
診断書をもらうことは、ゴールではなくスタートです。
- 医師の診断書で正式な休職が可能になり、心身を休める時間を確保できます。
- 給与が出ない期間も、条件を満たせば傷病手当金の支給対象となり、経済的な不安を軽減できます。
- 十分な休養の後、そのまま復職するだけでなく、転職や環境調整を考えるきっかけにする人も多くいます。
「診断書=終わり」ではなく、回復の第一歩です。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
心療内科の診断書に関するよくある質問
心療内科の診断書に関するよくある質問を紹介します。
- 診断書は初診でもらえますか?
- 症状が明確で、医師が「直ちに休職が必要」と判断した場合は、初診でも発行されることがあります。しかし、うつ病や適応障害などは慎重な判断が必要な場合もあり、数回の通院と経過観察を経てから発行されるのが一般的です。
- 診断書がもらえないことはありますか?
- はい、あります。医師が「医学的に見て休職の必要はない」と判断した場合は発行されません。
・症状が軽いと判断された場合→働きながら治療が可能と判断された場合。
・詐病が疑われる場合→症状がないのに診断書を要求するなど、不正な目的が疑われる場合。
・第三者からの請求→本人の同意なく、会社や家族が勝手に請求した場合(守秘義務違反となるため)。
- 診断書の日付はさかのぼって書いてもらえますか?
- 原則として、日付をさかのぼっての発行はできません。診断書は、あくまで「診察した日」の健康状態を証明するものです。「先週から休んでいる分も証明してほしい」と言われても、医師は過去の状態を診察していないため書けないのです。
ただし、すでに通院中でカルテ記録があり、明らかにその期間も症状があったと証明できる場合は例外的に対応できることもあります。
まとめ
心療内科の診断書が必要なのは、仕事のストレスやうつ症状で休職・欠勤を申請するとき、学校や試験を欠席・延期したいとき、保険申請や傷病手当金などの手続きのときです。医師が医学的な見地から就業・通学が困難であり休養が必要と判断した際に発行されます。
診断書に書かれる内容は、患者情報、傷病名、発病年月日、症状・経過、今後の見通し、休職の必要性、医療機関情報です。具体的な病名を会社に知られたくない場合は、医師に相談することでストレスによる体調不良など、ぼかした表現で記載してもらうことも可能です。
診断書をもらう流れは、心療内科・精神科の予約、医師への相談、診断書の発行依頼、診断書の受け取り、提出先への提出の5ステップです。オンライン診療で診察から診断書発行まで対応しているクリニックも増えています。
診断書の費用は一般的な休職・休学用で3,000円〜6,000円程度が相場で、健康保険の適用外となります。即日発行されることが多いですが、書類の種類や病院の混雑状況によっては数日かかる場合もあります。
診断書をもらったあとは、医師の診断書で正式な休職が可能になり、条件を満たせば傷病手当金の支給対象となり経済的な不安を軽減できます。診断書は終わりではなく回復の第一歩です。