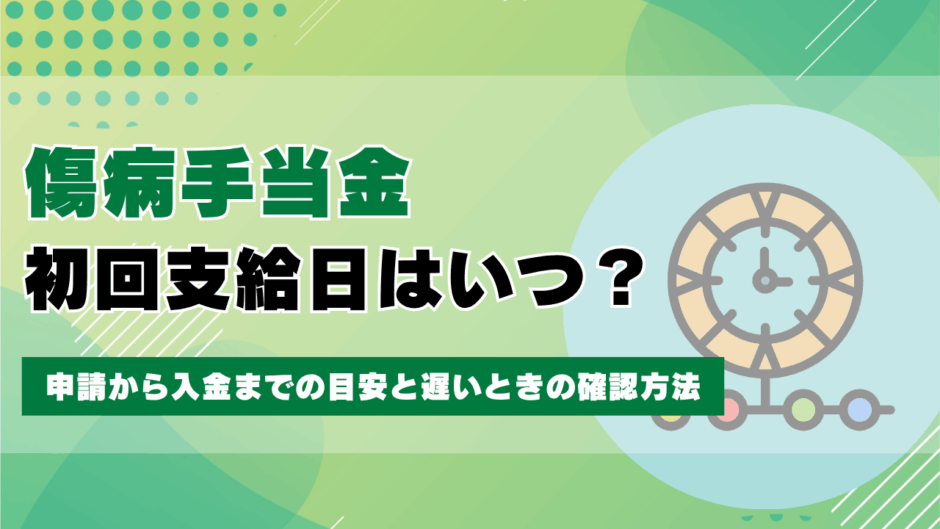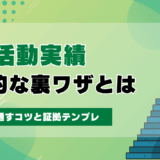傷病手当金を申請しても、なかなか振り込まれず不安になる人は少なくありません。特に初回は審査や確認に時間がかかるため、「いつ入金されるのか」「遅いけれど問題はないのか」と心配になる場面も多いでしょう。
この記事では、初回支給の目安期間や支給が遅れる理由、確認のタイミング、そして生活が厳しいときの対応策をわかりやすく解説します。仕組みを理解しておくことで、不安な待機期間を落ち着いて過ごせるはずです。
結論|初回支給日は申請から2〜6週間が目安
初回の傷病手当金の支給日は、申請からおおむね2〜6週間後が目安です。
保険者の種類や書類の状況によって前後するため、まずは「どのくらいで入金されるのか」の全体像を押さえておきましょう。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
初回支給までの一般的な期間
-1-1024x538.png)
傷病手当金を申請してから初回の振り込みまでの期間は、おおよそ2週間〜6週間が目安です。これはあくまで一般的な目安で、加入している保険者(協会けんぽ、健康保険組合)や書類の状況、時期によって前後します。
例として、全国健康保険協会(協会けんぽ)では、書類の到着(受付)後、おおむね10営業日前後で支給決定・支払処理が行われる目安が示されています(支部や時期により変動)。
健康保険組合(健保組合)は組合ごとに体制が異なり、初回は審査に時間を要するケースが多く、到着から数週間〜1か月程度を見込むのが一般的です。
初回申請は審査に時間がかかるため2回目以降より長くなる傾向があります。前提として、初回は「約1か月前後かかる」と見込んで生活費計画を立てておくと安心です。
2回目以降の支給が早い理由
初回に比べて2回目以降の申請が早いのは、初回のみ必要な確認作業(被保険者資格・医師証明・事業主証明など)の一部が既に完了しているためです。継続申請では休業実績の確認が中心となり、処理が簡略化されます。
また、傷病手当金の支給には「連続して労務に服していない3日間(待期)」の成立が必要です。有給休暇や公休日を含め、この3日間が連続していれば待期は認められます。
一度社会生活に復帰した後に社会的治癒と判断されるほど期間が空いて再発した場合は、継続ではなく初回扱いとなることがあります。この場合は再び初回同様の審査が必要となり、支給までの期間も初回に近い目安になる傾向です(判断は保険者によって異なる)。
遅いと判断できるタイミング
「申請から6週間超」がひとつの行動目安です。
以下に当てはまる場合は、状況確認をおすすめします。
- 申請から6週間以上経過しても支給決定通知書が届かない・入金もない
- 保険者や会社から不備連絡等が一切ない
- 同時期に申請した人には入金があるのに自分はない
不安を抱えたまま待つより、適切な時期に自ら確認する姿勢が大切です。
初回が遅くなる主な理由と2回目以降の違い
初回の支給が遅くなる背景には、保険者による詳細な審査や確認作業があります。
ここでは、初回と継続申請の違いや保険者ごとの処理ペースの差、提出時期によって支給日が変わる要因を紹介します。
初回は審査・確認が多く時間がかかる
初回は、保険者が被保険者資格の確認・医師の証明内容の確認・事業主(会社)証明の確認など、ゼロからの審査を行います。内容に疑義があれば照会が入るため、その分時間を要します。
退職後に傷病手当金を継続して受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 被保険者期間が通算12か月以上ある
- 退職日前までに待期(3日間)が完成している
- 退職日当日も労務不能である
退職日に出勤した場合、原則として継続給付の対象外となります。ただし、詳細な判断は保険者によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
また、けがの場合は「負傷原因届」、第三者行為(交通事故など)の場合は「第三者行為による傷病届」が必要になるケースがあります。これらの書類が未添付の場合、審査が滞る要因となるため注意が必要です。
保険者による処理ペースの違い
処理期間は加入先によって差が出ます。
- 協会けんぽ:協会けんぽでは、書類受付後、通常2〜3週間程度で支給決定・支払処理が行われることが多いとされています(支部や時期により前後します)。
- 健康保険組合:組合ごとの体制によって処理スピードに差があり、比較的早い場合もあれば、初回申請では到着から数週間〜1か月程度かかることもあります。
遅いからといって必ずしも不備があるわけではありません。
忙繁期や人員体制、照会対応の有無など、運用上の事情で前後する場合もあります。
提出のタイミングでも支給日は変わる
大型連休・年末年始前後や月末は処理開始が後ろ倒しになりやすいほか、会社経由提出の場合は社内確認・郵送工程で数日〜1週間超かかることもあります。
提出時期とルートを意識し、会社の発送予定日を事前に確認しておくと安心です。
通知が来ない・入金されないときの確認フロー
申請から何週間も経っても通知が届かない場合、どの時点で・どこに確認すればよいかを把握しておくことが大切です。
ここでは、支給決定通知と入金日の関係や通知が届かない主な原因を紹介し、確認をスムーズに進めるための手順をわかりやすくまとめます。
支給決定通知の到着と入金日の関係
支給決定が下りると、保険者から支給決定通知書(はがき/封書)が届きます。
ただし通知=即日入金ではありません。
通知到着から入金まで数日〜1週間程度のラグが生じることが多く、金融機関の営業日や月末タイミングによっても前後します。
| 通知書の到着日 | 入金される時期の目安 |
|---|---|
| 月曜日 | 同週の木曜〜金曜ごろ |
| 木曜日 | 翌週の火曜〜水曜ごろ |
| 祝日前 | 祝日明けの数営業日後 |
通知が届かないときに考えられる原因
支給決定通知が届かない場合、多くは事務処理の遅れや書類不備が関係しています。
申請済みでも音沙汰がないときは、まず以下のようなケースを疑いましょう。
- 審査中(照会対応や繁忙期で処理待ち)
- 会社未送付・到着遅延(社内決裁や郵送の都合による)
- 書類不備・差戻し(医師欄・事業主欄の記載漏れ、押印漏れ、日付不整合など)
「遅い」と感じたら、これらの可能性を念頭に置き、どの段階で止まっているかを順序立てて確認するのがポイントです。
【確認手順】会社→健保→再確認の3ステップ
通知が遅れている場合は、やみくもに電話をかけるより、順序を追って確認することが重要です。
以下の3ステップで確認を進めましょう。
- 会社へ確認:保険者への発送日・差戻しの有無を確認
- 保険者へ確認:受付日・審査状況・支給決定予定を確認
- 必要に応じ再対応:不備の補正・再提出を速やかに実施
この順序で進めれば、どこで処理が止まっているかを明確にでき、対応もスムーズです。
問い合わせ時に伝えるべき情報
確認の電話やメールを行う際は、必要な情報を正確に伝えることでやり取りがスムーズになります。
準備しておくとよい情報は以下の通りです。
- 健康保険証の記号・番号
- 氏名・生年月日
- 勤務先の正式名称
- 申請期間(○月○日〜○月○日分)
- 会社への提出日・担当部署
これらを伝えることで、相手がすぐにデータを特定でき、確認が早まります。
支給が遅れて生活が厳しいときの対応策
もし支給が遅れて生活が苦しくなった場合は、焦らずに公的な支援制度や支出の見直しを検討しましょう。
ここでは、利用できる貸付制度の概要や相談窓口、家計を一時的に立て直すための方法を紹介します。
公的貸付・支援制度を活用する
支給が遅れ、当面の生活費に困る場合は、民間ローンの前に公的制度を検討しましょう。代表例は生活福祉資金貸付制度(社会福祉協議会が窓口)です。
- 緊急小口資金:通常は10万円以内(原則一括)を上限とする貸付。
- 総合支援資金:生活再建までの月額貸付(世帯20万円以内/単身15万円以内 など)。
金額や期間は地域や運用状況で異なるため、まずはお住まいの社会福祉協議会に相談してください。
また、傷病手当金と老齢年金は併給調整の対象ではありません。一方で、同じ傷病によって「障害厚生年金」などを受け取る場合は、重複期間について調整(支給停止または差額支給)が行われることがあります。該当の可能性がある方は、加入している保険者に確認しておきましょう。
参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
家計の一時的な見直しをする
支給までの間は、固定費や日々の支出を一時的に見直すことも大切です。
通信費やサブスクなど、契約を調整できる項目から整理すると負担を減らしやすいでしょう。食費や日用品も「必要なものを優先して買う」意識を持つと無駄を抑えられます。
ただし、治療や通院に関わる支出は削らず、体調の回復を優先することが重要です。家計の見直しは、支給を待つ間に生活を安定させるための準備と考えましょう。
まとめ
傷病手当金の初回支給は、審査や書類確認に時間を要するため、2回目以降より遅れることが一般的です。申請から数週間経っても通知が届かない場合は、会社→保険者の順で確認し、必要に応じて再提出などの対応を行いましょう。
支給が遅れても焦らず、公的貸付制度の利用や一時的な家計見直しなど、生活を支える方法を検討しておくことが大切です。正しい知識と手続きを知っておけば、慌てずに対応できるでしょう。