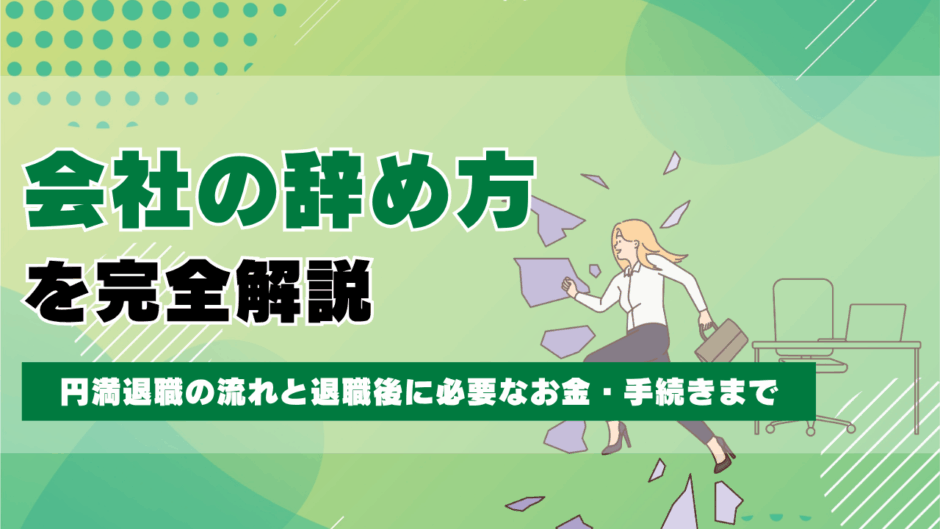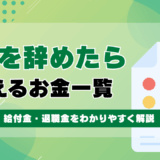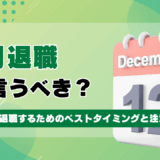会社を辞めることは労働者の自由な権利ですが、伝え方や手続きを誤るとトラブルや損失につながることがあります。特に初めての退職では、何から始めればよいか迷う人も多いでしょう。
この記事では、円満に辞めるための基本の流れと伝え方、退職後の手続きや失業保険の受け取り方をわかりやすく解説します。スムーズに準備を進めるための参考にしてください。
まず押さえておきたい「会社を辞める」基本ルール
まずは、退職に関する基本ルールを押さえて、落ち着いて準備を進めましょう。
ここでは、円満に辞めるための3つのポイントを紹介します。
退職の申し出は2週間前が原則
民法第627条では、期間の定めのない雇用契約の場合、退職の申し出は2週間前までに行えば良いと定められています。つまり、あなたが「辞めます」と伝えてから2週間が経過すれば、会社の合意がなくても雇用契約は終了します。
ただし、有期雇用(契約社員など)の場合は、契約期間の途中で原則として退職できません。労働契約法第17条に基づく「やむを得ない事由」があるときのみ認められます。
多くの会社では就業規則で「退職の申し出は1か月前まで」などと独自のルールを定めています。法的な効力では民法が優先されますが、円満退職を目指すならできるだけ早めに伝えるのが社会人としてのマナーです。
参考:宮城労働局(厚生労働省)「退職の申出は2週間前までに(PDF)」
参考:e-Gov法令検索「労働契約法第17条」
退職願・退職届の正しい使い分け
退職の意思を伝える書類には「退職願」と「退職届」があり、役割が異なります。
- 退職願:退職を「お願い(申請)」する段階の書類。承諾前なら撤回できる可能性あり。
- 退職届:退職の「最終意思」を通知する書類。提出後は原則撤回不可。
円満退職を目指すなら、まず上司に口頭で意思を伝え、退職日が確定してから退職届を提出するのが一般的です。
書面で残すことで「言った・言わない」のトラブルを防げます。
有給休暇の消化と退職日の決め方
-1024x538.png)
残っている年次有給休暇の消化は労働者の権利です。会社は原則として取得申請を断ることはできない仕組みになっています。
時季変更権は労働基準法第39条に定められていますが、退職の場合は代替勤務日を指定できないため、実際には行使されることがほとんどありません。そのため、退職時の有給休暇は基本的に希望どおりに取得できるでしょう。
引継ぎ期間を踏まえ、最終出社日 ⇒ 有給消化 ⇒ 退職日の順で逆算しましょう。
▼退職までの主な流れ(申し出〜最終出社まで)
| 期間 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 退職3ヶ月〜1.5ヶ月前 | 退職意思の決定、上司へ相談 | 直属上司にアポイント⇒対面が基本 |
| 退職1ヶ月前 | 退職届提出、引継ぎ開始 | 就業規則の期日を確認し計画的に開始 |
| 退職2週間前〜 | 関係者への挨拶、私物整理 | 社外先へ後任紹介もセットで実施 |
| 最終出社日 | 返却物提出、受領物確認 | 社員証・PC返却、源泉徴収票など確認 |
上司への伝え方・言い出し方のコツ
退職は伝え方で印象が大きく変わります。
ここでは、トラブルを避けるための基本・代替手段・引き止め対応を整理します。
最もトラブルになりにくい伝え方
最もスムーズなのは直属上司へ対面で伝えることです。アポイントは「お時間をいただきたいことがあります」など、やさしい言い方で伝えましょう。
切り出しは「お忙しいところ恐縮です。これまでのご支援に感謝しています。一身上の都合により退職させていただきたく存じます。」のように、感謝の言葉を添えて簡潔に伝えるのがポイントです。
言い出しにくいときの代替方法
対面で話すのが難しい場合は、まず面談をお願いするメールを送り、そのうえで直接話す流れにするのが丁寧です。
どうしても対面での面談が困難なときは、書面やメールで退職の意思を伝えても問題ありません。書面やメールであれば、送信日や内容が記録として残るため、「聞いていない」といったトラブルを防げます。
テレワークが中心の職場でも、できるだけビデオ会議などで顔を合わせて話す機会を設けることが望ましいです。
引き止められたときの対応
退職を伝えた際に引き止められることは少なくありません。そんなときは、まず「ありがたいお話ですが、退職の意思は固まっております」と結論から伝えるのが効果的です。
そのうえで、「○月末での退職を希望しております」と具体的な日付を提示し、話を前に進めましょう。感情的にならず、冷静かつ丁寧に対応することが大切です。
それでも強い引き止めが続く場合は、最終手段として内容証明郵便で退職届を送付する方法もあります。書面を通じて正式に意思を伝えることで、法的にも退職の効力を確実に示せます。
退職日までにやるべき手続き・準備チェックリスト
上司に退職の意思を伝えたら、次は最終出社日に向けて具体的な準備を進めましょう。
ここでは、退職日までに必ず済ませておきたい準備や確認項目を紹介します。
業務の引継ぎと情報整理
円満退職のために最も大切なのが、丁寧な引継ぎと情報整理です。まず、担当していた業務内容をすべてリストアップし、手順や注意点をまとめたマニュアルを作成しましょう。
主要な取引先の担当者・連絡先、進行中の案件の進捗状況なども文書化しておくと安心です。口頭での説明も併せて行うことで、抜け漏れを防ぎスムーズな業務の引継ぎができます。
会社に返却するもの・受け取るもの
退職日には、会社から貸与された物品をすべて返却し、退職後の手続きに必要な書類を受け取る必要があります。
- 返却するもの:健康保険証、社員証・入館証、貸与PC・スマートフォン・制服、自分の名刺、経費で購入した備品など
- 受け取るもの:離職票(1・2)、雇用保険被保険者証、源泉徴収票、基礎年金番号通知書(※2022年4月以降は年金手帳の新規発行なし/既存手帳は有効)
離職票や源泉徴収票は、退職後に自宅へ郵送されるケースも多いです。受け取り時期や発送方法については、事前に人事担当者へ確認しておきましょう。
有給休暇・清算の最終確認
退職間際は、有給休暇の消化や給与精算など、金銭に関する確認も忘れてはいけません。
まずは有給休暇の残日数と消化予定を最終確認し、上司や人事とスケジュールの認識を合わせましょう。また、最終給与に含まれる社会保険料の控除期間、未払い残業代の有無、通勤費や立替経費の精算状況なども確認が必要です。
特に住民税は、最後の給与から一括で天引き(特別徴収)される場合と、退職後に自分で納付(普通徴収)する場合があります。どちらの扱いになるかを経理・総務担当に確認しておくと安心です。
退職後に必要な手続きと「もらえるお金」の種類
会社を辞めた後は、健康保険・年金・税金などを自分で手続きします。
手続きが遅れると、保険が使えなかったり支給が遅れたりすることもあるので注意しましょう。
健康保険の切り替え
退職後は、会社の健康保険が使えなくなるため、自分で加入先を選ぶ必要があります。
主な選択肢は次の3つです。
- 任意継続被保険者制度(最長2年)
退職前の健康保険をそのまま継続できる制度。保険料は原則2倍ですが、上限があるため高所得者は2倍にならない場合もある。※ - 国民健康保険
前年の所得を基準に市区町村が保険料を計算。自治体の窓口やサイトで試算が可能。 - 家族の扶養に入る
配偶者などが加入する健康保険に扶養として入る方法。収入条件を満たす必要がある。
任意継続の申請期限は退職翌日から20日以内(必着)です。期限を過ぎると加入できないため注意しましょう。
※保険料上限は「協会けんぽ」の場合に適用されます。健康保険組合に加入していた人は、組合ごとに上限や算定方法が異なるため確認が必要です。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」
年金・住民税の切り替えタイミング
厚生年金は退職と同時に資格喪失となるため、14日以内に国民年金へ切り替えが必要です。
住民税は前年所得に対する後払い方式のため、退職後も納付義務があります。
最終給与で一括天引きされるか、後日届く納付書で支払うかを、事前に経理へ確認しておきましょう。
参考:日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
参考:総務省「地方税制度|個人住民税」
失業保険をもらうまでの流れ
失業保険は、ハローワークで求職の申込みを行い、離職票を提出したあと、7日間の待期期間を経て支給が始まります。
自己都合で退職した場合は、待期後に原則1か月の給付制限が設けられます。ただし、過去5年以内に3回以上の自己都合退職などを繰り返している場合や、懲戒解雇などの理由による離職では、3か月の給付制限となります(2025年4月改正後の規定)。
一方、会社都合の退職では給付制限がなく、待期期間が終了すればすぐに手当を受け取れます。
▼退職後1〜3か月の手続きスケジュール
| 時期 | 手続き内容 |
|---|---|
| 退職直後(14日以内) | 健康保険・年金の切り替え |
| できるだけ早く | ハローワークで求職申込み |
| 申請後7日間 | 待期期間(支給なし) |
| 約1ヶ月後 | 初回認定日/会社都合はこの後支給開始 |
| 1〜3ヶ月後 | 自己都合の給付制限終了後に支給開始 |
参考:厚生労働省「基本手当について」
参考:厚生労働省「令和6年雇用保険制度改正(令和7年4月1日施行分)について(PDF)」
まとめ
会社を辞めるときは、感情のままに行動せず、法律で定められたルールや社内手続きを理解して進めることが大切です。上司への伝え方ひとつで印象が変わり、退職後の人間関係にも影響します。
また、健康保険や年金の切り替え、失業保険の申請など、退職後の手続きも忘れずに行いましょう。順序立てて準備すれば、トラブルを避けながら円満に退職できます。