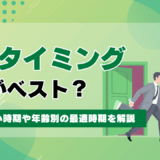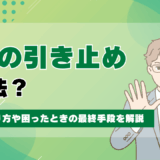任意継続とは、退職後も最長2年間在職中に加入していた健康保険に個人で加入し続けられる制度です。申請期限は退職日の翌日から20日以内と厳格で、保険料は全額自己負担で約2倍になりますが、扶養家族の人数が増えても保険料が増額されない点が国民健康保険との最大の違いです。
この記事では、任意継続の基礎知識、保険料のしくみ、被扶養者の条件、国保・家族の扶養との比較、手続きの流れまで解説します。
保険の任意継続についての基礎知識
任意継続とは、退職後も最長2年間、在職中に加入していた健康保険に個人で加入し続けられる制度です。これにより、退職後も在職中とほぼ同等の保険給付(傷病手当金、出産手当金を除く)を受けることができます。
参考:全国健康保険協会「任意継続とは」
加入できる人の条件
任意継続に加入するには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
- 申請期限の要件: 退職日の翌日から20日以内に申請手続きを完了すること。
- 被保険者期間の要件: 退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
参考:全国健康保険協会「任意継続の加入条件について」
申請期限は資格喪失日(退職翌日)から20日以内
申請期限は退職日の翌日から20日以内と厳格に定められています。1日でも過ぎると原則として加入資格を失うため、注意が必要です。
加入先は協会けんぽ or 企業の健保組合
任意継続で加入し続ける健康保険は、在職時に加入していた制度を継続する形となります。
- 在職中に「協会けんぽ」に加入していた場合は、退職後も協会けんぽの任意継続となります。
- 大企業などの独自の「健康保険組合」に加入していた場合は、その健保組合の任意継続となります。
期間は最長2年
任意継続の期間は、最長で2年間です。ただし、以下のいずれかに該当した場合は、その時点で資格を喪失し、任意継続は終了となります。(参考:全国健康保険協会「任意継続被保険者の資格喪失」)
- 任意継続被保険者となった日から2年を経過したとき
- 保険料を納付期日までに納付しなかったとき
- 就職して他の健康保険の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 死亡したとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出た場合(令和4年1月制度改正)
以前は、一度任意継続に加入すると原則2年間やめることはできませんでしたが、制度改正により、本人が希望すればいつでも(申し出が受理された月の末日に)資格を喪失できるようになりました。これにより、保険料の安い国民健康保険に切り替えたい場合や、家族の扶養に入れるようになった場合に、柔軟に対応できるようになっています。
保険料のしくみと相場感
任意継続の保険料は、在職中と計算方法が大きく異なります。
- 保険料の計算基準
退職時の標準報酬月額(退職時の給与を基に決定される)に、保険料率を掛けて計算されます。 - 保険料の負担
在職中は会社と折半していましたが、任意継続では全額自己負担となるため、保険料は約2倍になります。 - 保険料の上限
協会けんぽの場合、標準報酬月額に上限(現在30万円)が定められています。そのため、高所得者(退職時の給与が30万円を超えていた人)は、上限額で計算される任意継続の方が、前年所得に応じて計算される国民健康保険よりも保険料が安くなる可能性があります。
参考:全国健康保険協会「保険料について」
被扶養者はつけられる?
任意継続制度を利用した場合でも、在職中と同様に扶養家族(配偶者や子どもなど)を被扶養者として加えることが可能です。
国民健康保険(家族の人数に応じて保険料が増える)とは異なり、任意継続では扶養家族の人数が増えても保険料が増額されない点が、この制度を選ぶ際の最大のメリットとなります。
任意継続でも家族を「被扶養者」にできる条件(年収基準・同居要件)
任意継続でも、扶養家族の保険料は不要です。これは国民健康保険(家族全員分の保険料が必要)と比較した際の大きなメリットです。
扶養家族とするには、以下の主な条件を満たす必要があります。
- 年収基準: 家族の年間収入が130万円未満であること。
- 同居要件: 75歳未満で、主に被保険者(本人)によって生計を維持されていること。
扶養に入れないケースと確認書類
以下の場合は、扶養の条件から外れます。
- 家族の年間収入が130万円以上ある場合。
- 家族が別の健康保険に加入している場合。
- 家族が後期高齢者医療制度に加入している場合(75歳以上など)。
家族を扶養に入れる際は、扶養家族の収入証明書類(前年の源泉徴収票の写しなど)が必要です。
任意継続 vs 国民健康保険 vs 家族の扶養(比較の考え方)
退職後の健康保険の選択は、主に「扶養家族の有無」と「前年の所得」の2つで決まります。
| 項目 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 |
|---|---|---|---|
| 保険料の計算基準 | 退職時の標準報酬月額 | 前年の所得 | 不要(家族の保険料に加算なし) |
| 扶養家族の保険料 | 不要(大きなメリット) | 必要(家族全員分の保険料が必要) | – |
| 保険料の上限 | あり(高所得者に有利) | 上限額まで青天井 | – |
| 判断の軸 | 扶養家族が多い、または前年所得が高い場合 | 前年所得が低い場合、または単身の場合 | 自身に収入がない、または非常に少ない場合 |
高所得者で扶養家族が多い場合は任意継続が有利、前年の所得が低い場合は国民健康保険が有利、自身の収入がない場合は家族の扶養に入るのが最も有利となります。
手続きの流れと必要書類
任意継続は申請期限が短いため、退職が決まったらすぐに手続きの準備を始めましょう。
申請ステップ
- 書類入手: 加入していた健康保険組合または協会けんぽのウェブサイトから「任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードします。
- 記入: 申出書に必要事項を記入します。
- 提出: 資格喪失日から20日以内に、健康保険組合または協会けんぽに書類を提出します。
- 納付: 決定された保険料を納付します(初回は通常、申請時または指定期日に一括納付)。
- 保険証受取: 納付確認後、新しい保険証が送付されます。
必要書類
- 任意継続申請書(申出書)
- 本人確認書類
- 振込先の口座情報
- (扶養家族がいる場合)扶養家族の収入証明
退職から保険証切替までのつなぎ
退職日をもって、会社の健康保険証は使えなくなります。新しい保険証が届くまでの間、万が一病院にかかる場合は、一旦医療費を全額自己負担し、後日、新しい健康保険証と領収書をもって申請することで、自己負担分(3割)を超える差額分の払い戻しを受けることができます。
参考:全国健康保険協会「医療費の全額を負担したとき(療養費)」
まとめ
任意継続とは、退職後も最長2年間在職中に加入していた健康保険に個人で加入し続けられる制度で、退職後も在職中とほぼ同等の保険給付を受けることができます。加入条件は、退職日の翌日から20日以内に申請手続きを完了すること、退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があることの2つです。
保険料は退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けて計算され、在職中は会社と折半していましたが任意継続では全額自己負担となるため約2倍になります。協会けんぽの場合は標準報酬月額に上限があるため、高所得者は国民健康保険よりも保険料が安くなる可能性があります。
被扶養者は在職中と同様につけることが可能で、扶養家族の人数が増えても保険料が増額されない点が国民健康保険との最大の違いです。扶養の条件は、家族の年間収入が130万円未満であること、75歳未満で主に被保険者によって生計を維持されていることです。
手続きは、書類入手、記入、退職日の翌日から20日以内に提出、保険料納付、保険証受取の流れです。退職後の健康保険で損をしたくない方はぜひ参考にしてみてください。