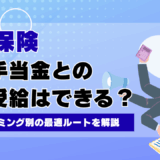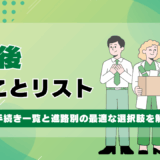教育訓練給付金は、厚生労働大臣が指定する講座を修了した際に受講費用の一部がハローワークから支給される公的制度です。専門実践教育訓練は給付率が最も高く、就職等で70%に増額され年間上限56万円、さらに賃金が上昇した場合は80%で年間上限64万円まで支給されます。
この記事では、教育訓練給付金の仕組みと目的、3つの区分、対象講座、受給対象、給付率・上限、申請方法、失業保険との併用まで解説します。
教育訓練給付金とは?制度の仕組みと目的
教育訓練給付金は、働く方々が主体的にスキルアップやキャリアチェンジを図り、雇用の安定と再就職の促進を支援することを目的とした公的制度です。
厚生労働大臣が指定する講座を修了した際に、受講費用の一部がハローワーク(雇用保険)から支給されます。
教育訓練給付金の3つの区分とは
この制度には、目的に応じて「専門実践」「特定一般」「一般」の3つの種類があり、それぞれ給付の手厚さが異なります。
| 専門実践教育訓練 | 労働者の中長期的なキャリア形成に資する訓練が対象。給付率が最も高く、業務独占資格(看護師、美容師など)や専門性の高いデジタルスキルなどが含まれます。 |
| 特定一般教育訓練 | 労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する訓練が対象。大型自動車免許や介護職員初任者研修など、早期の再就職に役立つ講座が中心です。 |
| 一般教育訓練 | その他の雇用の安定・就職の促進に資する、幅広い講座が対象。簿記検定、ITパスポート、大学院の修士課程などが含まれます。 |
教育訓練給付金の対象講座とは
給付金の対象となるのは、厚生労働大臣が指定した教育訓練講座のみです。ご自身の受けたい講座が対象かどうかは、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認できます。
専門実践訓練には、オンラインで受講できるデジタル関連のスキル講座も多数含まれており、働きながらでも学びやすい環境が整備されています。
教育訓練給付金の受給対象
給付金は、雇用保険の加入期間や状況によって、在職中・離職後でそれぞれ条件が異なります。
在職中の条件
- 被保険者期間
受講開始日時点で、雇用保険の被保険者期間が原則として3年以上必要です。ただし、初めて受給する場合は2年以上で対象となります(一般訓練は初回1年以上)。 - 会社補助との関係
会社が受講費用を全額負担している場合は、給付金制度の対象外となることがあります。給付金は、あくまで「受講者本人」の費用負担を軽減するための制度です。
離職後の条件
- 利用できる期間
離職された方も、離職日の翌日から1年以内に受講を開始すれば、支給要件期間(原則3年、初回は2年/1年)を満たしていれば受給対象となります。 - 失業保険との関係
失業保険(基本手当)を受給している間は、原則として教育訓練給付金を受給できません。ただし、専門実践教育訓練に限り、45歳未満で失業状態など一定の要件を満たす方には、訓練中の生活費を支援する「教育訓練支援給付金」(失業手当日額の60%相当)が別途支給される制度があります。
対象外になりやすいケース
- 講開始日時点で、雇用保険の被保険者期間が要件に満たない場合。
- 厚生労働大臣の指定を受けていない講座を受講した場合。
- 受講者本人ではなく、会社が受講費用を全額負担した場合。
教育訓練給付金はいくら戻る?給付率・上限とは
給付額は、受講者が実際に負担した費用(授業料、入学金など)に対し、訓練の種類ごとに定められた給付率と上限額で計算されます。
給付率・上限の違い
| 種類 | 給付率 | 年間上限額 |
|---|---|---|
| 一般教育訓練 | 20% | 10万円 |
| 特定一般教育訓練 | 40% (資格取得・就職で50%に増額※) | 20万円 (資格取得・就職で25万円に増額※) |
| 専門実践教育訓練 | 50% (資格取得・就職で70%に増額、さらに賃金上昇で80%に増額※) | 40万円 (資格取得・就職で56万円に増額、さらに賃金上昇で64万円に増額※) |
※特定一般・専門実践の給付率増額は、令和6年10月1日以降に受講を開始した場合に適用されます。
対象経費とは
給付の対象となるのは、受講者本人が教育訓練施設に支払った授業料、入学金、教材費などです。これらは「受講費用」とみなされます。一方、交通費、宿泊費、PCの購入費、受講期間外の検定料などは、原則として対象外です。
自己負担の見え方
給付金制度は、原則として費用を「立替→支給」という形をとります。
- 受講者はまず、教育訓練施設に受講費用を全額支払います。
- その後、訓練修了後(専門実践は6ヶ月ごと)にハローワークに申請し、給付金を受け取ります。
費用の立て替えが必要となるため、あらかじめ資金を準備しておく必要がありますが、教育ローンの利用や分割払いとの併用も可能です。
教育訓練給付金の申請方法
専門実践訓練や特定一般訓練は、受講開始前にハローワークでのキャリアコンサルティングが義務付けられているため、申請手続きが煩雑になりがちです。
受講前の手続き
専門実践訓練と特定一般訓練は、受講開始日の2週間前までに以下の手続きを完了させる必要があります。
- 受給資格確認
ジョブ・カードと必要書類を添付し、ハローワークで受給資格の確認手続きを行います。 - キャリアコンサルティング
ハローワーク指定のコンサルタントによる面談を受け、「ジョブ・カード」を作成します。(これが必須要件です。)
受講中の変更手続き
休学、訓練期間の変更、転校など、受講内容に重要な変更があった場合は、速やかにハローワークや教育訓練施設に届け出を行う必要があります。
修了後の申請
訓練を修了したら、給付金を受け取るための申請を行います。
- 専門実践訓練
受講開始から6ヶ月ごとに、所定の期間内に申請を行います。 - 特定一般訓練・一般訓練
訓練修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に、ハローワークに必要書類を提出します。
手続きには必ず期限があるため、申請が遅れないよう注意が必要です。
教育訓練給付金は失業保険と併用できる?
教育訓練給付金と失業保険(基本手当)の併用については、多くの人が誤解しがちなポイントです。結論から言うと、併用は可能です。
| 教育訓練給付金 | 受講費用の一部を補助する制度 |
| 失業保険(基本手当) | 失業中の生活費を支える制度 |
この二つは目的が異なるため、両方の条件を満たしていれば、失業保険を受け取りながら、教育訓練給付金で受講費用の補助を受けることができます。
併用できないのは「教育訓練支援給付金」
併用できないのは、専門実践教育訓練の受給者向けに生活費を支援する「教育訓練支援給付金」です。
Q. 現在離職中で、専門実践教育訓練を受講予定です。雇用保険の基本手当が支給終了になると生活費が心配です。専門実践教育訓練を受講することで受けられる給付金はありますか。
A. (前略)ただし、専門実践教育訓練給付金の受給資格者が基本手当の給付を受けることができる期間は、教育訓練支援給付金は支給されません。基本手当の支給が終了したあとに給付を受けることができます。
つまり、生活費の支援は「基本手当」か「教育訓練支援給付金」のどちらか一方しか受け取れず、基本手当が優先されます。
教育訓練支援給付金は雇用保険の基本手当の日額の60%に相当する額が給付されます。
(※令和7年3月31日以前に受講開始した場合は80%)
失業保険の受給権を失わないための手続きが必要
教育訓練を受けることで失業保険の受給期間(原則離職日の翌日から1年間)が過ぎてしまうことを防ぐため、訓練開始前にハローワークで受給期間の延長手続きを行うことが重要です。
この手続きにより、失業保険の受給権を長期間(最長4年間)温存しておくことができます。
まとめ
教育訓練給付金は、働く方々が主体的にスキルアップやキャリアチェンジを図り、雇用の安定と再就職の促進を支援する公的制度で、厚生労働大臣が指定する講座を修了した際に受講費用の一部がハローワークから支給されます。
3つの区分は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練です。専門実践は中長期的なキャリア形成に資する訓練で給付率が最も高く、特定一般は速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する訓練、一般はその他の雇用の安定・就職の促進に資する幅広い講座が対象です。
受給対象は、在職中の場合は受講開始日時点で雇用保険の被保険者期間が原則3年以上必要で初回は2年以上、離職後の場合は離職日の翌日から1年以内に受講を開始すれば受給対象となります。
教育訓練給付金を活用してスキルアップしたい方はぜひ参考にしてみてください。