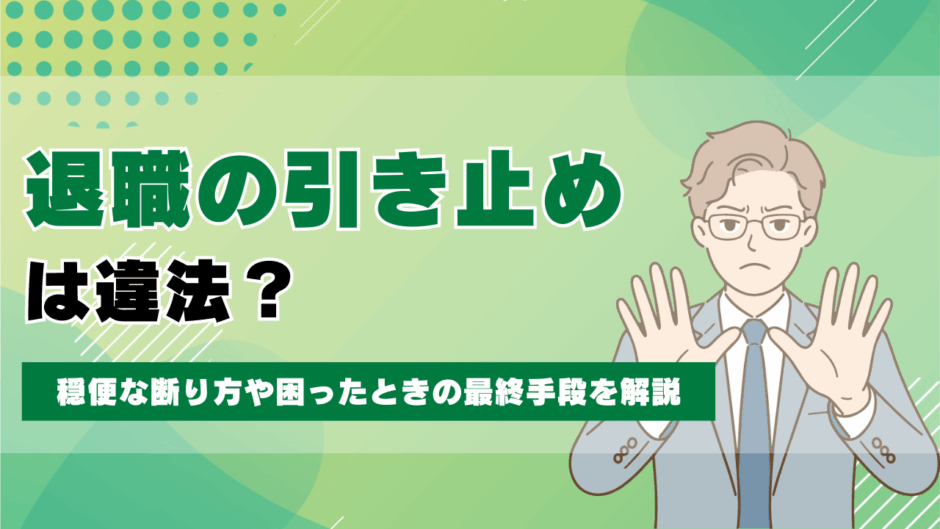退職の引き止めは、正当な説得と違法な引き止めに分かれます。労働者には退職の自由が法律で保障されており、民法の2週間ルールでは退職の意思表示から2週間が経過すれば会社の合意がなくとも雇用契約は終了します。事前に証拠を残し、穏便な断り方を準備することが重要です。
この記事では、退職の引き止めの定義、民法の2週間ルール、事前にできる対策、穏便に断る基本フレーズ、引き止めが長引く場合の最終手段まで解説します。
退職の引き止めとは?正当な説得と違法な引き止めの違い

退職の引き止めとは、労働者が退職の意思を伝えた後、会社側がその退職を思いとどまらせようと働きかける行為です。この行為は、「正当な説得(提案)」と「違法な強制(脅迫)」の2つに大別されます。
就業規則と民法の原則(退職の自由/2週間ルール)の確認
まず、労働者には「退職の自由」が法律(憲法第22条)で保障されており、会社の引き止めに法的な強制力はありません。
- 民法の原則(2週間ルール)
期間の定めのない雇用契約の場合、退職の意思表示から2週間が経過すれば、会社の合意がなくとも雇用契約は終了します。
参考:e-Gov法令検索「民法第627条」
- 就業規則
多くの会社は就業規則で「1ヶ月前または2ヶ月前までに申告」と定めていますが、これは円満退職のための努力義務であり、法律上は民法が優先されます。
参考:厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」
正当な引き止め|条件提示・配置転換など提案ベース
正当な引き止めとは、労働者の退職理由を聞いた上で、会社側が労働条件の改善を提案する行為です。
例えば、給与アップ(カウンターオファー)、昇進、希望部署への配置転換、業務内容の軽減などを提示して、労働者の意思決定を促します。これは企業として優秀な人材を失わないための合理的な行為であり、違法ではありません。
違法になり得る引き止め|脅し・退職届不受理・有給拒否
以下の行為は、労働者の権利を侵害するものであり、違法性が高くなります。
| 脅迫・威圧 | 「損害賠償を請求する」「懲戒解雇にする」などと脅す。 |
| 退職届の不受理 | 労働者の退職の意思表示を拒否し、退職届の受け取りを拒む、または破棄する。 |
| 有給休暇の拒否 | 退職日までの有給休暇の消化を、業務に支障が出ることを理由に全面的に認めない。 |
| 責任転嫁 | 「君が辞めると会社が潰れる」など、過度に責任感を煽り、精神的に追い詰める。 |
退職を引き止められそうだと思ったら?事前にできる対策
退職交渉を有利に進め、引き止めによるトラブルを未然に防ぐためには、事前の準備が不可欠です。
対策1|退職の申出をしたという証拠を残す
引き止めが長期化した場合、「いつ、誰に退職を伝えたか」が重要な証拠となります。
例えば、上司に退職の旨を口頭で伝えた後、「本日は退職の件でご相談させていただきました」といった内容のメールを送付し、その写しを保存しておきましょう。また、面談をした場合は日付や内容を簡潔に記録しておくのがおすすめです。もし脅迫や違法な引き止めに遭いそうな場合は、自己防衛のために面談内容を録音することも有効です。
対策2|会社規程を守っていることを確認する
会社側から「規則違反だ」と指摘されないよう、事前に確認しておきましょう。
退職手続きに関しては、就業規則上の申告期限(例:1ヶ月前)を守って申告したり、有給の残日数を把握し、退職日までの消化計画を立てておくと安心です。また、退職後も機密情報の保持義務を負うことを理解し、データなどを持ち出さないよう徹底しましょう。
参考:厚生労働省「モデル就業規則」
対策3|適切なスケジュール設計にしておく
会社側の反論(「後任がいない」など)を封じるために、具体的で現実的なスケジュールを提示します。
最終出社日は有給消化期間を見越した日を設定し、引継ぎ資料の目次や後任者への説明スケジュール案を作成しておくと良いでしょう。有給消化案に関しては、「〇月〇日〜〇月〇日は有給消化に充当させていただきます」と明確に提示しておくと安心です。
退職の引き止めを穏便に断る基本フレーズ3選
退職交渉で最も重要なのは、「退職の意思が固い」ことを明確に、かつ感情的にならずに伝えることです。会社側の引き止め提案に対しては、以下のフレーズを基本に毅然とした態度で断りましょう。
入社日が確定している場合の断り方
「すでに転職先が決まっており、〇月〇日の入社日を延期できないため、貴社へのご恩は承知しておりますが、今回の決意は変わりません。引継ぎは〇月〇日までに完了させますので、ご理解いただけると幸いです。」
このフレーズは、交渉に第三者(転職先)の存在を持ち込むことで、退職の決定が「不可逆的である」ことを会社に示します。会社が「退職を拒否すると、転職先に迷惑がかかる、または法的な問題につながる」と認識するため、最も引き止めが効きにくい断り方です。
あくまで引継ぎの誠意は見せつつも、スケジュールは譲れないという強い意思を伝えましょう。
年収・役職などカウンターオファーの断り方
「ご提案いただいた給与(または役職)については大変ありがたいお話ですが、今回の退職は金銭的な理由ではなく、新しい分野に挑戦したいというキャリアの方向性に関わる決断です。心から感謝しておりますが、お受けできません。」
カウンターオファー(昇給や昇進の提示)は、引き止めの典型的な手法です。ここで提示される条件は、「なぜ今まで提示されなかったのか」を冷静に考える必要があります。
退職の理由が業務内容への不満や人間関係にある場合、単に給与が上がっても根本的な問題は解決しません。安易に応じると、後で約束が反故にされたり、退職を申し出た人間として社内での立場が悪くなったりするリスクもあります。退職理由が「キャリアの方向性」にあることを明確に伝え、議論の余地をなくしましょう。
体調・家庭事情の伝えての断り方
「(可能であれば)今回の休養は、医師からも明確に指示された体調維持のためであり、現在の業務を継続することは難しいと判断しました。まずは療養に専念させていただきたく、ご理解ください。」
「体調不良」や「家族の介護・サポート」といった会社が介入できない個人の領域を理由にすることで、引き止めの余地をなくすことができます。特に、医師の診断書を提出している場合は、「医学的に休養が必要」という客観的な根拠があるため、それ以上議論を続けることは会社側にとってもリスクとなります。
情に訴えかけられても、自身の健康と生活が最優先であることを貫きましょう。
退職の引き止めが長引く場合の最終手段
穏便な交渉や意思表示をしても、会社が退職を認めない、あるいは嫌がらせが続く場合は以下の最終手段を検討しましょう。
| 手段 | 強み | おすすめの状況 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 退職代行 | 直接交渉を遮断できる | 心身限界/出社困難 | 法的交渉は弁護士のみ可 |
| 労基署・労働局相談 | 行政指導の後ろ盾 | 違法行為が疑われる | 事実関係の記録が必須 |
| 内容証明郵便 | 意思表示の公的証明 | 受理拒否・破棄がある | 文面・日付ミス厳禁 |
手段1|退職代行サービスを利用する
自分で交渉する精神的な負担が大きい、あるいは加害者と顔を合わせるのが困難な場合、退職代行サービスを利用できます。サービス業者は労働者の代理として退職の意思表示を会社に伝達し、交渉を代行します。これにより、出社せずに退職を完了させることが可能です。
ただし、弁護士資格のない業者は会社との法的な交渉(未払い賃金請求など)ができないため、サービスの対応範囲を事前に確認する必要があります。
手段2|労働基準監督署へ相談・通報する
会社側が違法な行為(例:退職を盾にした有給休暇の拒否、不当な損害賠償の脅迫など)を行っている場合、労働基準監督署(労基署)へ相談・通報することができます。
労基署は労働基準法に基づいて、会社に対して是正指導や勧告を行う行政機関です。特に労働基準法違反が明らかな場合は、行政指導を促すことで引き止め行為を止める効果が期待できます。
参考:厚生労働省「労働基準監督署の役割」
手段3|内容証明郵便で退職届・通知を送付する
退職届を直接受け取ってもらえない、または「受理していない」と会社が主張しそうな場合、内容証明郵便を利用します。これは、「いつ、誰が、どんな内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれるため、民法の「2週間ルール」を適用するための最も強力で確実な証拠となります。
これにより、会社の合意がなくても、意思表示から2週間が経過した時点で雇用契約が終了したことを法的に証明できます。
参考:日本郵便「内容証明」
退職の引き止めに関するよくある質問(FAQ)
ここでは、退職の引き止めに関するよくある質問を紹介します。
- 「後任が決まるまで退職不可」と引き止められたら?
- 「後任が決まるまで退職不可」と言われても、法的には退職できます。 後任の採用・育成、および業務の引継ぎは会社の責任であり、労働者が負う義務ではありません。
もちろん、引継ぎへの誠意は見せるべきですが、後任の有無にかかわらず、民法の2週間ルールが適用されます。会社側の論理に屈せず、退職日が固いことを明確に伝えてください。
- 「損害賠償だ」と脅されたら?
- ほとんどの場合、違法性が高い脅し文句です。 労働者が会社に損害を与える目的で一方的に退職した場合など、特殊なケースを除き、損害賠償が認められることは極めて稀です。
このような脅迫に遭った場合は、一人で悩まず、すぐに労働基準監督署や法テラスに相談しましょう。
- 退職日を前倒し・後ろ倒しにする交渉は可能?
- 交渉は可能です。前倒しで早く辞める場合は、会社が引継ぎを理由に拒否する権利があります。会社との合意が必要です。
一方、後ろ倒しで遅く辞める場合は、会社と合意すれば可能です。有給消化期間が足りない場合など、円満退職を目指すために交渉すべきです。ただし、会社が拒否しても、民法の2週間ルールが適用されるため、会社は2週間を超えて労働者を拘束できません。
まとめ
退職の引き止めは、正当な説得と違法な引き止めの2つに大別されます。正当な引き止めは給与アップや配置転換など提案ベースで合理的な行為ですが、違法になり得る引き止めは脅迫・退職届の不受理・有給休暇の拒否などで労働者の権利を侵害します。
労働者には退職の自由が法律で保障されており、会社の引き止めに法的な強制力はありません。民法の2週間ルールでは、退職の意思表示から2週間が経過すれば会社の合意がなくとも雇用契約は終了します。事前にできる対策は、退職の申出をしたという証拠を残す、会社規程を守っていることを確認する、適切なスケジュール設計にしておく、の3つです。
引き止めが長引く場合の最終手段は、退職代行サービスを利用する、労働基準監督署へ相談・通報する、内容証明郵便で退職届を送付するの3つです。後任が決まるまで退職不可と言われても法的には退職でき、損害賠償の脅しはほとんどの場合違法性が高い脅し文句です。退職の引き止めで悩んでいる方はぜひ参考にしてみてください。