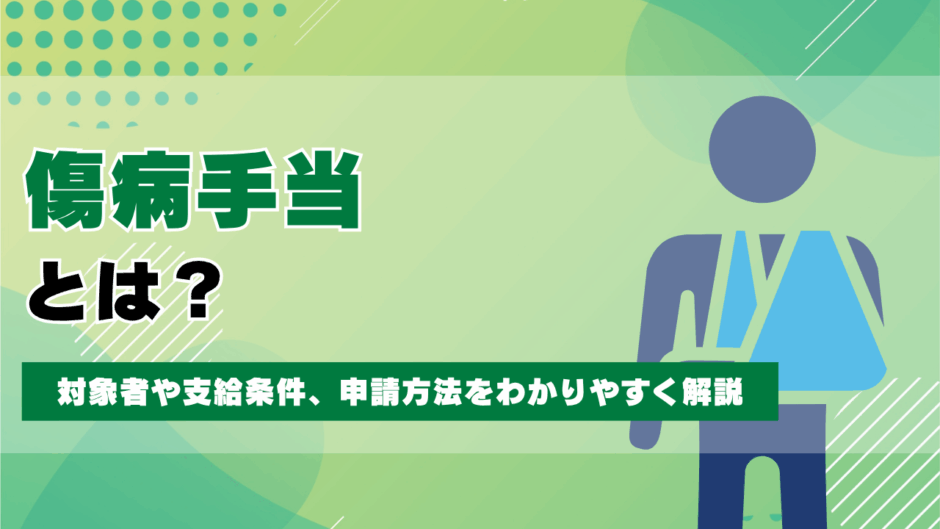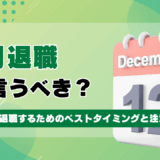傷病手当金とは、会社員や公務員が業務外の病気やケガで仕事を休む際、給与が受けられない期間の所得を補填する健康保険の給付金制度です。支給金額は月給の約3分の2で、最長1年6ヶ月まで受給できます。
この記事では、傷病手当金の対象者と支給条件、支給金額の計算方法、申請方法と必要書類、会社員・自営業・退職後の違い、注意点まで解説します。
傷病手当金とは?対象者と条件
「傷病手当」とは、一般的に、会社員や公務員などが加入する健康保険から支給される「傷病手当金」を指すことが多いです。本記事では、この「傷病手当金」について詳しく解説します。
「傷病手当」と「傷病手当金」の違い
非常に紛らわしいですが、「傷病手当」という名称の制度は雇用保険にも存在します。こちらは失業中に病気やケガで求職活動ができなくなった場合に支給されるものです。多くの会社員の方が休職時に利用するのは、健康保険の「傷病手当金」です。
傷病手当金は、業務外の病気やケガが原因で長期間仕事を休まなければならなくなった時、給与が受けられない、または減額される間の所得を補填し、被保険者と家族の生活を保障するセーフティネットとしての役割を果たします。
傷病手当金の対象者
傷病手当金の対象となるのは、勤務先の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)に加入している「被保険者本人」です。会社員や公務員などがこれにあたります。
- 勤務先の「健康保険(社会保険)」に加入している会社員、公務員、契約社員、パート、アルバイトの方。
- 自営業者やフリーランスなどが加入する「国民健康保険」の加入者。
- 被保険者の「扶養家族」。
この制度は、上記の対象者が「業務外の病気やケガ」の療養のために仕事を休業し、その結果、給与が受けられない(または減額される)場合に、生活保障として所得を補填する目的で設けられています。
ただし、対象者であっても、実際に支給を受けるためには、次に説明する「4つの必須条件」をすべて満たす必要があります。
傷病手当が支給される4つの条件
傷病手当金を受給するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 業務外の病気やケガ | 仕事中・通勤中の事故は労災保険の対象となるため除外されます。美容整形なども対象外です。 |
| ② 連続して4日以上の休業 | 療養のために休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を経た後、4日目以降の休業日が支給対象となります。(※待期期間は有給休暇や土日・祝日も含む) |
| ③ 給料が支払われていない | 休業期間中に給与の支払いがないことが条件です。給与があっても、傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。 |
| ④ 医師の証明がある | 医師が「労務不能」と判断した証明(申請書への記入)が必要です。 |
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当金の支給金額はいくら?計算方法をシミュレーション
支給額の目安は、おおよそ「月給の3分の2」です。正確な1日あたりの支給額は「(支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額) ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。
【平均標準報酬月額が30万円の場合】
300,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約6,667円/日
この金額が、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月まで受け取ることが可能です。(※途中で復職した期間はカウントされません)
給与やボーナス(標準報酬月額)によって支給額が前後するため、正確な金額はご自身が加入している健康保険組合(協会けんぽなど)で確認しましょう。
参考:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当の申請方法と必要書類
申請手続きは、本人、医師、事業主(会社)の3者が行う必要があります。
傷病手当の申請手順
勤務先または加入している健康保険組合のウェブサイトから「傷病手当金支給申請書」を入手します。
自分(本人)が氏名や振込先口座などを記入し、会社(事業主)に勤務状況・給与支払状況を、医師に労務不能であった期間の証明を、それぞれ依頼し記入してもらいます。
すべての書類が揃ったら、加入している健康保険組合に郵送などで提出します。
審査後、問題がなければ指定口座に入金されます。(※通常、給与の締め日ごとに1ヶ月単位で申請します)
傷病手当の必要書類
必要な書類は、原則として「傷病手当金支給申請書」です。この申請書は、通常4枚綴り(または4つのパート)で構成されており、以下の3者がそれぞれ必要事項を記入・証明する形式になっています。
- 本人(被保険者)が記入する欄
申請者の氏名、保険証の番号、振込先口座情報などを記入します。 - 医師が証明する欄
療養を担当した医師が、傷病名や労務不能と認めた期間などを記入します。(これが「意見書」の代わりとなります) - 事業主(会社)が証明する欄
勤務先が、休業した期間の勤務状況や、給与の支払い状況を記入・証明します。(これが「給与証明書」の代わりとなります)
これら3者すべての記入・証明が揃った「傷病手当金支給申請書」を健康保険組合に提出します。
※一般的に、加入する健康保険組合によっては、初回申請時などに本人確認書類(マイナンバーカードの写し)や、振込先口座がわかるもの(通帳の写し)の添付を別途求められる場合があります。
参考:全国健康保険協会「健康保険傷病手当金支給申請書」
傷病手当金はいつから・いつまで支給される?期間とタイミング
傷病手当金の支給には、開始時期、期間、申請のタイミングに関して明確なルールがあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給開始日 | 連続休業4日目から |
| 支給期間 | 最長1年6ヶ月(途中で復職・再発の場合も通算) |
| 支給時期 | 申請受付後、約10営業日で振り込み(協会けんぽの場合) ※加入する健康保険組合により異なります。 |
傷病手当金の会社員・自営業・無職での違い
傷病手当金は、加入している公的医療保険の種類によって扱いが異なります。
| 立場 | 傷病手当の有無 | 補足 |
|---|---|---|
| 会社員(社会保険加入) | あり | 健康保険から支給される |
| 自営業(国民健康保険) | 原則なし | 一部自治体では「国保傷病手当金制度」あり |
| 無職・退職者 | 条件付きで支給 | 退職後も「在職中と同じ傷病」であれば可 |
退職後でも傷病手当がもらえるケースはある?
退職後も傷病手当金(継続給付)を受け取れる場合があります。ただし、それには以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
- 退職日時点で、傷病手当金を受給しているか、受給できる状態(連続3日間の待期期間を終え、労務不能な状態)であること。
- 退職日当日に出勤していないこと。
特に3つ目の「退職日に出勤しない」点は非常に重要です。たとえ挨拶のためであっても、退職日に出勤してしまうと「労務不能ではない」と判断されて継続給付の権利を失うため、特に注意が必要です。
傷病手当金に関するよくある質問(Q&A)
- 傷病手当はアルバイト・パートでももらえますか?
- 社会保険に加入していれば支給対象になります。
- 傷病手当と失業保険は同時にもらえますか?
- 同時には受け取れません。傷病手当金は「働けない状態」、失業保険(雇用保険)は「働ける状態」であることが受給の前提であるため、両立しません。
傷病手当金の受給中は、失業保険の受給期間の延長手続きをしておきましょう。
- 傷病手当は確定申告が必要ですか?
- 非課税所得のため申告不要です。
傷病手当を受け取る際に知っておきたい3つの注意点
傷病手当金を申請・受給する際には、以下の点に注意が必要です。
- 医師の「労務不能」の証明が必須
傷病手当金は、本人の自己申告だけでは受給できません。必ず、療養を担当した医師による「仕事に就くことができない(労務不能)」という医学的な証明(申請書への記入)が必要です。
- 申請には時効がある
傷病手当金の申請権利は、療養のために休んだ日(給与が支払われなかった日)ごとに発生し、その翌日から2年で時効となります。申請が遅れると給付金を受け取れなくなるため、休業が長期化する場合は、給与の締め日ごと(1ヶ月ごと)など、定期的に申請手続きを行うことが重要です。
- 有給休暇や給与との調整がある
待期期間(最初の3日間)に有給休暇を使うことは可能です。しかし、支給対象日(4日目以降)に有給休暇を取得して給与が支払われた場合、その日の傷病手当金は支給されません。ただし、支払われた給与額が傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。
まとめ
傷病手当金とは、会社員や公務員が業務外の病気やケガで長期間仕事を休む際、給与が受けられない期間の所得を補填する健康保険の給付金制度です。対象者は勤務先の健康保険に加入している会社員、公務員、契約社員、パート、アルバイトで、自営業者の国民健康保険加入者は原則対象外です。
支給される4つの条件は、業務外の病気やケガ、連続して4日以上の休業、給料が支払われていない、医師の証明があるです。支給金額は月給の約3分の2で、最長1年6ヶ月まで受給可能です。
申請は、傷病手当金支給申請書に本人、医師、事業主の3者が記入・証明して健康保険組合に提出します。連続休業4日目から支給開始され、申請から約1〜2ヶ月後に振り込まれます。
退職後でも、退職日までに1年以上の被保険者期間がある、退職日時点で受給しているか受給できる状態、退職日当日に出勤していないの3条件を満たせば継続給付を受けられます。注意点は、医師の労務不能証明が必須、申請は休んだ日の翌日から2年で時効、有給休暇や給与との調整があることです。