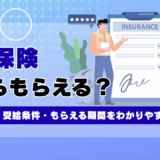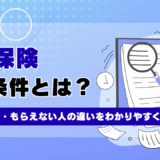会社を辞めたあと、「退職金のようなものがもらえる」と聞いたことはありませんか?
そうした制度が「退職給付金」と呼ばれるもので、退職後の生活を支えるための大切なお金です。ただし、企業によって内容や条件が大きく異なり、「知らなかった」で損をすることもあります。
この記事では、退職給付金の基本から制度の種類、もらえる条件、確認方法までをわかりやすく整理しました。失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)との違いや注意点も含めて解説していきます。

人事労務コンサルティング会社経験後、1000人規模の医療法人で人事課長として、社会保険手続き、規程整備、助成金、労務のDX化など幅広く対応。その後社労士事務所を開業し、ベンチャー企業から大企業のバックオフィスのサポートを行なっている。
退職給付金の基本と退職金・失業保険との違い
退職給付金と一言でいっても、その中身はさまざまです。
まずは「退職給付金とは何か?」という基本と、「退職金」「企業年金」「失業保険」との違いを整理しておきましょう。制度の全体像をつかんでおくことで、後の理解がスムーズになります。
退職給付金の定義と支給の目的
退職給付金とは、会社が制度に基づいて支給する退職後の金銭的給付の総称であり、退職金や企業が関与する年金制度などが該当します。
支給の目的は主に以下の3つです。
- 長期勤続への報酬として
- 退職後の生活安定のため
- 離職者の経済的不安の軽減
なお、支給されるかどうかは会社の制度に依存しており、法律で必ず支払う義務があるわけではありません。
退職金・企業年金・失業保険との違い
退職給付金と混同しやすいのが、「退職金」「企業年金」「失業保険」です。 それぞれの違いは次の表をご覧ください。
| 項目 | 退職給付金 | 失業保険 |
|---|---|---|
| 支給元 | 勤務していた会社 | 国(ハローワーク) |
| 必ずもらえるか | 会社の制度次第(ない会社もある) | 条件を満たせば必ずもらえる |
| 加入条件 | 特になし(企業制度次第) | 雇用保険に加入していたか |
| 支給時期 | 退職直後が多い | 申請後1週間〜数ヶ月後 |
| 目的 | 長期勤務への報酬・老後資金 | 離職後の生活支援 |
どんな制度がある?退職給付金の種類と仕組み
退職給付金の制度にはさまざまな形があり、企業の規模や方針によって導入される仕組みが異なります。
ここでは、代表的な3つの制度を紹介していきます。
確定給付企業年金(DB)
の資金の流れ-1024x538.png)
確定給付企業年金(DB)は、企業があらかじめ定めた算出方法に基づき、給付額が一定のルールで決まる制度です。
企業が運用責任を負い、従業員に一定額を支給する仕組みになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付額の決定主体 | 企業が責任を持って設計 |
| 掛金の拠出主体 | 主に企業(従業員は原則不要) |
| 運用リスク | 企業が負担 |
| メリット | 将来の給付額がわかるため、老後の設計がしやすい |
| デメリット | 企業側の負担が重く、制度廃止の傾向にある |
多くの大手企業がかつて採用していましたが、現在は制度維持の負担から縮小傾向にあります。
確定拠出年金(DC)
の仕組み-1-1024x538.png)
確定拠出年金(DC:Defined Contribution)は、企業や従業員が定期的に掛金を拠出し、その運用結果によって将来の給付額が決まる制度です。
いわば「自己責任型の年金制度」で、運用成果がよければ受け取れる金額も増えていきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 給付額の決定主体 | 運用結果により変動(企業は保証しない) |
| 掛金の拠出主体 | 企業または企業+従業員 |
| 運用リスク | 従業員本人が負う |
| メリット | 自分で運用方針を選べる、転職しても持ち運べる |
| デメリット | 投資知識がないと運用に不安が残る |
DC制度には企業型と個人型があり、個人型は「iDeCo(イデコ)」として知られています。
中小企業退職金共済・厚生年金基金など
中小企業では、独自の制度を持つのが難しいことから、外部機関による共済制度を利用するケースが一般的です。 代表的な制度を以下にまとめてみました。
中小企業退職金共済(中退共)
- 政府が運営する中小企業向けの共済制度
- 掛金は企業が毎月納付し、従業員が退職すると直接共済から給付が行われる
- 約36万社が加入しており、もっとも普及している制度のひとつ
特定退職金共済(特退共)
- 商工会議所などが提供する退職金共済制度
- 加入条件や掛金の仕組みは団体によって異なる
厚生年金基金(現在は原則新規設立不可)
- かつて存在した企業年金の一種で、現在は廃止・移行が進められている
- 過去に加入していた人は「企業年金連合会」などで記録を確認可能
参考:厚生労働省「中小企業退職金共済制度」
退職給付金を受け取れる条件と手続きの基本
退職給付金は、誰でも自動的にもらえるわけではありません。
企業が制度を導入しているか、どのくらい勤続していたか、退職理由は何かといった条件によって、支給の有無や金額が大きく変わります。
ここでは、受け取るために必要な条件と、実際の手続きの流れを解説します。
制度の有無・勤続年数・退職理由の影響
退職給付金をもらえるかどうかは、会社に制度があるか、どのくらい勤めていたか、どのように辞めたかで決まります。
特に以下のポイントを確認しておきましょう。
- 退職給付制度があるかどうか
- 勤続年数はどれくらいか(例:勤続3年以上で支給対象になる会社が多い)
- 退職理由が自己都合か、会社都合か(減額・不支給の可能性あり)
支給の有無は会社の制度に大きく依存しています。まずは自分の会社のルールを確認することが第一歩です。
申請の流れと給付時期の目安
退職給付金の申請は、基本的には退職後に会社からの案内に従って進めます。ただし、企業年金や共済制度など、外部機関を通す場合は別途手続きが必要なこともあります。
手続きの流れは以下の通りです。
- 退職給付金の一般的な流れ(企業型の場合)
- 退職届の提出・退職確定
- 会社から退職金(または年金)に関する書類が届く
- 指定の申請書に記入して返送
- 数週間〜1ヶ月程度で給付金が振込まれる
企業年金連合会や共済制度を利用していた場合
- 退職後に自分で年金機構や共済団体へ請求が必要
- 住所変更や口座情報の登録・確認を忘れずに行うこと
退職給付金を確認するときの注意点
退職給付金がある場合、退職後の手続きで注意すべき点がいくつかあります。 申告ルールをきちんと理解することが重要です。
退職前後に必ずチェックしたい書類は以下の通りです。
- 就業規則・退職金規程(会社に制度があるかを確認)
- 退職時の説明資料(退職金の額や支給時期の案内)
- 離職票(失業保険の申請に必要、退職理由の記載に注意)
- 共済制度・企業年金の加入証(転職・年金請求時に必要)
これらの書類は、退職後すぐに手続きで必要になるものが多いため、退職前にコピーをとっておくと安心です。
まとめ
退職給付金は、会社の制度や勤続年数、退職理由によって支給条件や金額が大きく変わります。確定給付型(DB)と確定拠出型(DC)の仕組み、中小企業向けの共済制度も押さえておくと、退職後の備えがより具体的になります。
まずは、自分の会社の就業規則や退職金規程に目を通してみてください。制度を正しく理解しておくことで、退職後の不安や損失を最小限に抑えられます。