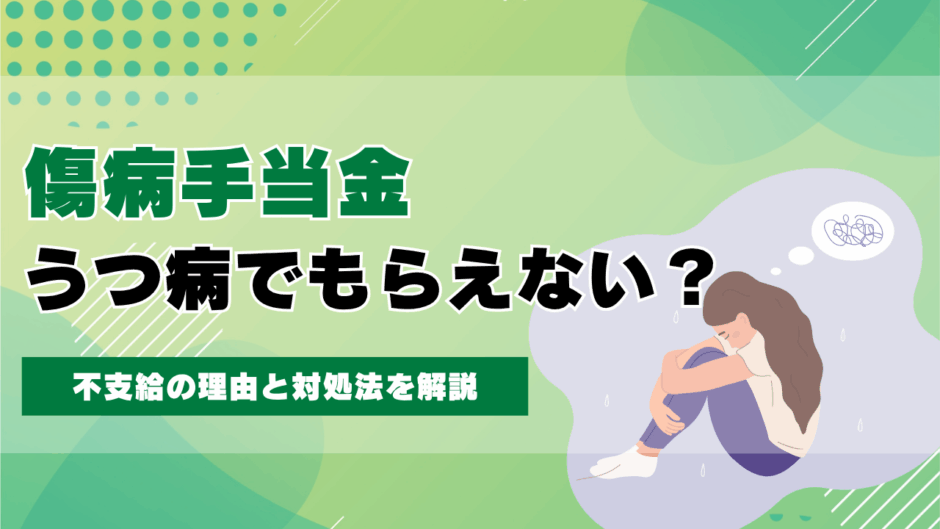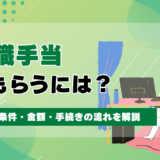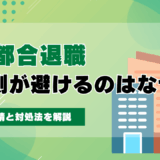うつ病で仕事を休んでいるのに、「傷病手当金が支給されなかった」「審査に通らなかった」と悩む方は少なくありません。実は、病名だけで不支給になることはほとんどなく、多くの場合は書類の不備や手続き上のミスが原因です。
この記事では、うつ病で傷病手当金がもらえない主な理由と、再申請や審査請求などの正しい対処法を解説します。仕組みを理解し、安心して治療と生活を両立させるための参考にしてください。
うつ病でも傷病手当金は受け取れる?支給の基本条件を確認

心身の不調で仕事を休むことになったとき、生活の支えとなるのが傷病手当金です。この制度は健康保険の被保険者が対象で、うつ病や適応障害といった精神疾患も、医師が「仕事ができない状態(労務不能)」と判断すれば支給の対象になります。
「うつ病だからもらえないのでは?」と不安に感じる方もいますが、病名で判断されることはありません。
重要なのは、次の4つの条件を満たしているかどうかです。
- 健康保険の被保険者であること(退職後は継続給付の要件を満たす必要あり)
- 医師から労務不能と証明されていること
- 休業中に会社から給与が支払われていないこと
- 待期は連続3日間の休業が成立条件。2日休業後に3日目に就労すると待期は成立しません(途中出勤で中断)。
これらを満たしていれば、正社員・契約社員・パートなど雇用形態にかかわらず申請できます。
▼傷病手当金の主な支給条件
- 保険加入: 退職前に勤務先の健康保険に加入していること。退職後は「資格喪失後の継続給付」の要件を満たす必要あり。
- 労務不能: 医師により「就労できない」と診断されていること。診断書の内容が曖昧だと支給が認められない場合も。
- 給与未支給: 休業中に給与が支払われていないこと。有給休暇を取った日は対象外。
- 待期期間: 3日間連続で仕事を休むと4日目から支給対象。途中で出勤すると待期がリセットされる。
<ポイント>
うつ病という診断名ではなく、「働ける状態にあるかどうか」で判断されます。
書類不備や日付のずれがあると審査で不支給になることもあるため、医師・会社双方との連携が欠かせません。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
うつ病で傷病手当金がもらえない主な理由
傷病手当金が承認されない場合、その多くは「書類の不備」「手続きミス」「審査上の判断」のいずれかが原因です。
どのケースに当てはまるかを確認し、原因を特定することが次の対応につながります。
医師の診断書や証明書類の不備
最も多いのは、提出書類に不備があるケースです。審査は書類上で行われるため、記入漏れや内容の矛盾は不支給に直結します。
例えば「労務不能」の表現が曖昧だったり、診断期間と実際の休業日が一致していなかったりすると、審査側は働けない状態と判断できません。また、会社の証明日数と本人の申告にズレがある場合も注意が必要です。
まずは診断書・事業主証明などの提出書類一式を見直し、抜け漏れがないか確認しましょう。
働けると判断されるケース
休職中でも「働ける」と見なされると支給対象外になります。この制度は、あくまで病気やケガで労務不能な人の生活を支えるものだからです。
短時間の在宅ワークやアルバイトなど、収入を得ていた場合は「就労」と判断される可能性があります。
SNS発信や趣味の活動が直接不支給の理由になることはありませんが、医師の診断内容と矛盾する行動が確認されると、労務不能の判断に影響する場合があります。療養期間中は回復を最優先にしましょう。
退職・保険切替時の手続きミス
傷病手当金は、在職中の健康保険から支払われるため、資格を失うと原則として支給は止まります。
退職後も継続して受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ退職日の前日までに支給を受けている又は受けられる状態(待期完成・労務不能等)にあること
- 退職後も労務不能が継続し、休業期間に賃金の支払いがないこと(他給付との重複不可、支給期間は通算最長1年6か月)
国民健康保険には新規の傷病手当金制度は原則ありませんが、継続給付は退職時の保険者から支給されます(要件を満たす場合)。任意継続の期間に新規で傷病手当金の申請はできません。
ただし、退職時点で「支給中」又は「受けられる状態(待期完成・労務不能・賃金支払なし)」であれば、退職時の保険者から継続給付を受けられます。
また、待期期間(連続3日間の休業)が退職前に完了していない場合は、継続給付の対象外となります。退職日も出勤していないことが条件であり、待期未完成のまま退職すると支給は認められません。
申請が通らないときの対処法|再申請・審査請求の流れ
傷病手当金の不支給通知が届くと、落ち込む方も多いでしょう。しかし、その時点で諦める必要はありません。
不支給になった理由を正確に把握し、正しい手順を踏むことで、決定が覆る可能性は十分にあります。
不支給理由を確認する
まず最初に行うべきは、「なぜ支給されなかったのか」という理由を正確に把握することです。理由がわからなければ、正しい対処はできません。 手元に届いた「不支給決定通知書」には、支給できない理由が記載されています。
もしその内容を読んでも具体的に理解できない場合は、ご自身が加入している健康保険組合や、全国健康保険協会(協会けんぽ)の窓口に直接問い合わせましょう。その際は、「どの書類の、どの点が条件を満たしていないと判断されたのか」を具体的に確認することが重要です。
診断書・証明書類を修正・再提出する
不支給の理由が書類の不備であると判明した場合、その点を修正して再提出することで、支給が認められるケースは多くあります。審査で判断が保留になった部分について、正確な情報で補足する作業だと考えましょう。
例えば、医師の診断書の内容が不十分だと指摘されたなら、担当の医師に事情を説明し、「労務不能と判断した医学的な理由」などをより具体的に追記してもらうようお願いしてください。日付の誤りや期間の整合性が取れていない場合は、会社の担当者や医師に連絡し、正しい情報に訂正してもらう必要があります。
審査請求・再審査請求を行う
書類を修正して再申請しても認められなかったり、審査の判断そのものに納得がいかなかったりする場合には、「審査請求」という不服申し立ての手続きがあります。これは、健康保険組合などの決定に対し、中立な第三者機関に改めて審査を依頼する制度です 。
審査請求は、不支給通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局(または支局)の社会保険審査官に申し立てます。必要な書類を揃えて申し立てを行い、再度審査を待ちます。もし、この社会保険審査官の決定にも納得できない場合は、さらに社会保険審査会に対して「再審査請求」をすることも可能です。
退職前後に注意すべきポイント
退職を挟むと、傷病手当金の手続きはさらに複雑になります。特に、退職前後のわずかな手続きのミスが、その後の支給を左右することも少なくありません。
安心して治療に専念するためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。
退職前に確認すべきこと
退職を決意したら、傷病手当金を受け続けるために、退職日までにいくつか確認しておくべき項目があります。スムーズな手続きのために、計画的に準備を進めましょう。
最も重要なのは、退職日までに傷病手当金の支給条件を満たしているかという点です。特に、連続3日間の休み(待期期間)が退職日までに完了しているかは必ず確認してください。
また、申請書には会社に記入してもらう「事業主の証明」欄があります。退職後は会社との連絡が取りにくくなる可能性もあるため、必要な証明は在職中に必ず依頼し、受け取っておくのが安心です。
退職日や健康保険の資格を失う日を正確に把握し、会社の担当者と共有しておくことが大切です。
退職後も支給されるケース
条件を満たせば、会社を退職した後も傷病手当金を受け取り続けることが可能です。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
制度を利用するには、「退職日までに同一の健康保険に継続して1年以上加入していること」と、「退職する時点で、実際に傷病手当金を受けているか、または受けられる状態にあること」が必要です。
この権利は、退職後の健康保険の種類にかかわらず、退職直前の健康保険から支給されます。ただし、市町村の国民健康保険に加入した場合は、原則として継続給付は受けられません。
退職後も定期的に通院し、医師から「労務不能」であることの証明を受け続けることで、最長1年6か月の期間、支給を受けられます。
失業保険との関係
休職を経て退職した場合、気になるのが「失業保険(雇用保険の基本手当)」との関係です。
結論として、傷病手当金と失業保険は同時に受け取れません。
理由は、両制度の目的が異なるためです。
- 傷病手当金:病気やケガで働けない人(労務不能)を支援
- 失業保険:働く意思と能力がある人(労務可能)を支援
したがって、まずは治療に専念し、働けない間は傷病手当金を利用します。体調が回復して「就労可能」となった時点で受給を終え、ハローワークで失業保険の申請に切り替えるのが一般的です。
また、傷病手当金の支給期間(最長1年6か月)が長引くと、失業保険の受給期間(原則1年)が過ぎてしまうことがあります。この場合は、ハローワークで「受給期間延長手続き」(最長3年間)を行い、権利を保っておくことが大切です。
参考:厚生労働省「基本手当について」
まとめ
うつ病でも、条件を満たしていれば傷病手当金は受け取れます。不支給になる多くの原因は、書類の不備や手続きミスです。
通知が届いたら理由を確認し、必要に応じて再申請しましょう。時間がかかる場合は、緊急小口資金などの公的支援も検討できます。焦らず一つずつ整理し、必要に応じて専門家へ相談することも大切です。