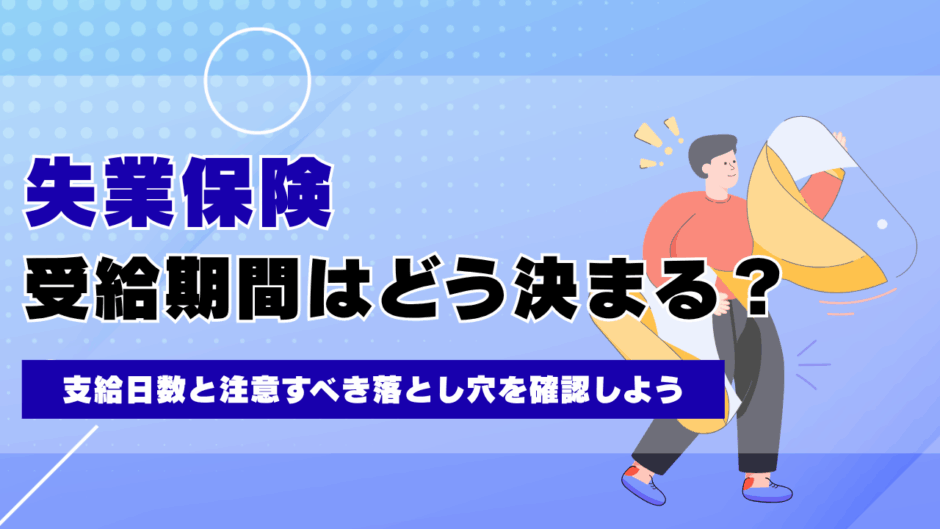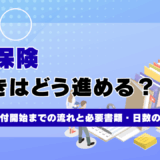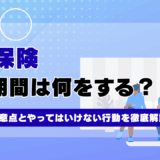失業保険(正式には「雇用保険の基本手当」)は、退職後の生活を支える大切な制度です。しかし、「自分は何ヶ月もらえるのか?」「満額もらえないこともある?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、失業保険の受給期間(支給日数)の決まり方と、よくある落とし穴についてわかりやすく解説します。年齢・退職理由・雇用保険の加入期間といった基本的な要素から、延長制度や注意点、確認方法まで丁寧に紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
失業保険の受給期間はどれくらい?支給日数の決まり方
失業保険でもらえる期間は、人によって大きく異なります。
ここでは、支給日数の決まり方と、「自分は何日もらえるのか」を判断する基本ルールを解説します。
支給日数の決まり方|年齢・退職理由・加入期間で変わる基準

支給日数は「年齢」「雇用保険に入っていた期間」「退職理由」によって決まります。特に自己都合と会社都合では、支給までの待機期間やもらえる期間が大きく異なるのが特徴です。
自分がどれに当てはまるかは、以下の早見表で確認できます。
自己都合退職の場合(年齢に関係なく加入年数で決まる)
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1〜10年未満 | 90日(約3ヶ月) |
| 10〜20年未満 | 120日(約4ヶ月) |
| 20年以上 | 150日(約5ヶ月) |
会社都合退職の場合(年齢別)
▼30歳以上35歳未満
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1〜5年未満 | 120日 |
| 5〜10年未満 | 180日 |
| 10〜20年未満 | 210日 |
| 20年以上 | 240日 |
▼35歳以上45歳未満
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1〜5年未満 | 150日 |
| 5〜10年未満 | 180日 |
| 10〜20年未満 | 240日 |
| 20年以上 | 270日 |
▼45歳以上60歳未満
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1〜5年未満 | 180日 |
| 5〜10年未満 | 240日 |
| 10〜20年未満 | 270日 |
| 20年以上 | 330日 |
▼60歳以上65歳未満
| 雇用保険の加入期間 | 支給日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日 |
| 1〜5年未満 | 150日 |
| 5〜10年未満 | 180日 |
| 10〜20年未満 | 210日 |
| 20年以上 | 240日 |
45歳以上60歳未満になると、加入年数が長いほど支給日数も大幅に増えるのが特徴です。特に20年以上勤務していた場合、330日(約11ヶ月)もの支給が受けられる可能性があります。ただし、60歳以上65歳未満では支給日数が240日に減少する点に注意が必要です。
特定受給資格者・特定理由離職者や就職困難者の特例日数
特定受給資格者・特定理由離職者や就職困難者に該当すると、通常より長い期間の失業保険を受け取れる特例があります。
特定受給資格者・特定理由離職者とは?
会社都合退職の中でも、より明確な理由がある場合に該当します。
具体的には、次のような事情がある場合です。
- 会社の倒産・事業所の閉鎖
- 解雇・雇い止め
- パワハラやセクハラによる退職
- 長時間労働や未払い残業など労働環境の問題
こうした事情がある場合、給付制限を受けない資格として扱われます。
就職困難者とは?
心身に障害がある方や、社会復帰にハードルのある方など、一般的な就職が難しいと判断された場合に認定されます。
具体的には、以下のような方が対象です。
- 身体障害・知的障害・精神障害により就職が困難な方
- 刑法等の規定により保護観察に付された方(ハローワークの判断による)
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方(ハローワークの判断による)
就職困難者に認定されると、被保険者期間に応じて最大300〜360日(約10〜12ヶ月)の支給が受けられます。
具体例で比較
例:Aさん(35歳、月給30万円、うつ病)
| 項目 | 通常の自己都合 | 就職困難者認定あり |
|---|---|---|
| 支給開始までの期間 | 約1〜1.5ヶ月(条件により変動)※ | 約7日後から |
| 支給日数 | 90日(3ヶ月) | 300日 |
| 支給総額(目安) | 約45万円 | 約150万円 |
→ 認定されると、100万円以上の差が出るケースもあります。
※2025年4月改正により、自己都合退職者の給付制限は従来の2ヶ月から原則1か月に短縮されました。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
受給期間を最大限活かすために知っておきたいこと
失業保険の受給期間は、ただ待っているだけでは十分に活かしきれません。
ここでは、受給期間を無駄なく使うために押さえておきたい実践的なポイントを紹介します。
受給期間中にバイトはできる?再就職したらどうなる?
失業保険を受給中でも、条件付きでバイトや副業は可能です。主なポイントは次のとおりです。
アルバイト・副業のルール
- 週20時間未満の労働であれば基本的にOK(雇用保険対象外)
- 収入がある場合、申告すれば一部減額支給される可能性も
- 申告しないと「不正受給」扱いになることもあるため注意!
週20時間未満であれば原則として受給可能ですが、収入が高すぎる場合は減額や支給停止になることもあります。必ずハローワークに申告しましょう。
再就職したらどうなる?
早期に就職が決まった場合、支給残日数に応じて「再就職手当」がもらえることがあります。
例:90日支給予定で30日分受給後に就職
→ 残60日×70% ≒ 約42日分の手当支給
認定日忘れや求職活動の記録漏れに注意
失業保険は、自動的にもらえるものではありません。「認定日」と呼ばれる指定日にハローワークへ出向き、就職活動の実績を報告することが義務です。
以下のようなミスがよく見られます。
- 認定日を忘れてハローワークに行かず、支給が1回飛んでしまった
- 活動実績の証拠(企業との連絡、応募履歴など)を記録していなかった
- 1回の求人検索だけで「活動1回」とカウントしたつもりになっていた
なお、認定日を無断で欠席した場合、「基本手当の不支給(その認定期間がまるごと)」になることがありますが、ハローワークに正当な理由があれば再調整も可能です。
受給期間の延長が認められるケース
失業保険の受給期間には原則として期限がありますが、特別な事情がある場合は延長が認められます。
ここでは、延長の対象となるケースや、手続きの流れをわかりやすく解説します。
病気・出産・介護など、やむを得ない事情があるとき
失業保険には、「すぐには働けない特別な事情」がある場合に、受給期間そのものを延長できる制度があります。
対象となるのは、以下のようなやむを得ない理由によって、求職活動ができないケースです。
- 妊娠・出産・産後の体調回復
- 病気やケガによる療養
- 家族の介護や看護
- 配偶者の海外勤務への同行 など
これらの事情があると、最大3年まで受給期間の延長申請が可能です。
特に、退職後すぐに働けないことが明らかであれば、早めに申請しておくことで損失を防げます。
参考:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
延長申請の方法と手続きのタイミング
受給期間の延長申請は、30日以上働けない状態になった日以降、できるだけ早く行うことが重要です。
制度上は、延長後の受給期間終了日(原則、離職日の翌日から4年以内)まで申請可能ですが、申請が遅れると本来もらえるはずの給付日数を受け取れなくなる可能性があります。
- 30日以上継続して働けない状態になったことを確認する
- 30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日以降早期にハローワークで「受給期間延長申請書」を提出する
- 事情を証明する書類を添付する(医師の診断書、母子健康手帳、介護認定証など)
- 申請が受理されると、最長3年間の延長が認められる
なお、申請は郵送や代理人による提出も可能です。ハローワークに事前連絡のうえ、必要書類を確認しましょう。
自分の受給日数を確認する方法
自分が何日間の失業保険を受け取れるかを事前に把握しておくことで、今後の行動計画が立てやすくなります。
ここでは、確認に必要な情報やチェックすべきポイントをご紹介します。
離職票・雇用保険被保険者証をチェック
自分が何日間の受給資格を持っているかは、まず手元にある書類で確認できます。
特に重要なのが次の2点です。
- 離職票(1・2)
- 雇用保険被保険者証
受給日数に影響するのは、「退職理由」と「雇用保険の加入期間」の2つです。離職票の記載が誤っていると不利になる可能性があるため、内容はしっかりチェックしましょう。
ハローワークで確認できる項目と注意点
書類だけで判断がつかない場合は、ハローワークで直接確認するのが確実です。求職申込の際に「受給資格決定」まで進めば、支給日数や手当額の説明を受けられます。
ハローワーク相談時に確認すべきこと
- 離職理由は「自己都合」か「会社都合」か
- 加入期間に不足がないか(複数社勤務の場合は合算の可否も)
- 特定受給資格者・特定理由離職者や就職困難者に該当する可能性があるか
- 申告内容に不備がないか
参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
まとめ
失業保険の受給期間は、退職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって異なります。支給日数の満額を受け取れないケースや、延長・拡大の特例があることも理解しておくことが大切です。
離職票や被保険者証で自分の受給資格を確認し、認定日や活動実績の管理も忘れずに行いましょう。「何日もらえるか」だけでなく、「確実に受け取るにはどうすべきか」まで意識することが、制度を活かすポイントです。